会社が個人に謝礼金を支払う際、適切な金額設定や税務処理に悩む担当者は少なくありません。「源泉徴収は必要か?」「消費税の扱いはどうなるのか?」といった疑問も多く、対応に困るケースが見られます。
しかし、正しい知識を身につければ、これらの課題は解決できます。本記事では、謝礼金の支払いに関する重要なポイントを解説します。勘定科目の選定方法、源泉徴収の必要性、消費税の取り扱いなど、実務に役立つ内容を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
会社が個人に謝礼金を払う手順
会社が個人に謝礼金を払う際の手順は、以下の3つのステップに分けられます。
- 謝礼金の目的と金額の明確化
- 社内規定や稟議書の作成
- 支払い方法の決定
これらの準備が整ったら、実際の支払いに移ります。金銭授受のトラブルを防止する観点から、謝礼金の支払いは銀行振り込みを推奨します。また、支払いが完了したら、最後に適切な勘定科目で経理処理を行ってください。謝礼金の性質によって、交際費や支払手数料などの科目を選択することになるでしょう。
会社が個人に払う謝礼金の事例

会社が個人に謝礼金を支払う場合、その性質によって適切な勘定科目が異なります。ここでは謝礼金の代表的な3つの事例を紹介し、それぞれの特徴と注意点を解説します。
事例①謝礼金が報酬に値する場合
報酬として扱われる謝礼金は、個人の専門的なスキルや知識に対して支払われるものです。たとえば、講演会の講師料などが該当します。その理由は講師が持つ専門知識や経験に対する対価だからです。講師は自身の専門性を活かしてサービスを提供しており、その労務の対価として謝礼金を受け取ります。
このような専門的なサービスへの支払いは、「支払報酬」として処理するのが適切です。このような専門的なサービスへの支払いは、「支払報酬」として処理するのが適切です。また、コンサルタントへのアドバイス料も同様です。コンサルタントの専門的な知見や助言に対する対価であり、一時的な役務提供に対する支払いであるため、報酬として取り扱われます。
事例②謝礼金が交際費に値する場合
交際費として扱われる謝礼金は、主にビジネス上の関係維持や円滑化を目的としたものです。たとえば、取引先を紹介してもらった際のお礼は交際費に該当します。これは、事業に関係のある者との親睦を深めるためのものだからです。取引先の紹介は直接的な役務提供ではなく、ビジネス上の好意や協力に対する感謝の表現になります。
また、このような支出は、事業の遂行に間接的に寄与するものとして「交際費」に分類されます。ビジネスチャンスを提供した際の感謝も同様です。これは直接的なサービスの対価ではなく、ビジネス関係の維持・強化を目的とした支出であるため、交際費として扱われます。
事例③謝礼金が支払手数料に値する場合
支払手数料として扱われる謝礼金は、業務に関連して発生する各種の手数料や報酬です。具体的には、通訳サービスなどへの謝礼が該当します。通訳サービスへの謝礼金は、特定の業務遂行に直接関連する専門的サービスの対価です。
通訳のように業務と直結するサービスへの支払いは、「支払手数料」として処理するのが適切です。また、業務委託契約に基づく報酬も同様に扱われます。これは、会社の業務の一部を外部に委託する際の対価であり、直接的に業務遂行に関わるサービスへの支払いとなるため、支払手数料として分類されます。
会社が個人に謝礼金を払う時の勘定科目
会社が個人に謝礼金を支払う際、謝礼金の性質や目的によって、正しい勘定科目が異なるため、慎重に判断する必要があります。ここでは、主な勘定科目とその特徴について解説していきます。
交際費
交際費は、事業関係者との親睦を深めるための支出です。ただし、個人への謝礼金を交際費として扱う場合には、いくつかの注意が必要です。まず、その支出が本当に事業に関係する交際費であるかを慎重に判断する必要があります。私的な付き合いによる支出は交際費として認められません。
次に、金額の妥当性も考慮しましょう。過度に高額な謝礼金は税務調査で問題となる可能性があるため、適切な金額設定が求められます。また、源泉徴収の要否も検討する必要があります。純粋な贈与であれば源泉徴収は不要ですが、役務提供の対価と解釈される場合には必要となることがあります。
さらに、支払いが実質的に報酬や手数料の性質を持つかどうかも確認することが重要です。適切な処理を行うことで、税務リスクを軽減し、健全な企業経営に貢献します。
支払手数料
支払手数料は、業務に関連して支払う各種の手数料や報酬を計上する勘定科目です。支払手数料は、通常の経費として全額損金算入が可能です。ただし、源泉徴収の対象となる場合が多いので注意が必要です。
支払手数料として処理する際は、その謝礼金が本当に業務に関連した専門的なサービスへの対価であるかを確認しましょう。単なる感謝の気持ちを表すものであれば、他の勘定科目が適切なケースがあります。
広告宣伝費・販売促進費
広告宣伝費や販売促進費は、商品やサービスの宣伝、販売促進のために支出する費用です。謝礼金がこれらの勘定科目で処理されるのは、主に以下のような場合です。
- インフルエンサーへの商品紹介依頼の謝礼
- 口コミ投稿やレビュー作成への謝礼
- 販売促進イベントの協力者への謝礼
広告宣伝費・販売促進費も通常の経費として全額損金算入が可能です。たとえば、インフルエンサーへの謝礼金の場合、単に商品を送っただけでなく、実際に宣伝活動が行われたことを示す証拠(投稿のスクリーンショットなど)を保管しておくと良いでしょう。ただし、広告宣伝費や販売促進費として処理する場合、その支出が本当に宣伝や販売促進の目的で行われたものかを明確にしなければなりません。
売上高
謝礼金を売上高として計上するケースは稀ですが、全くないわけではありません。たとえば、以下のような場合が考えられます。
- 会社の本業に関連するサービスの提供に対する謝礼
- コンサルティングへの謝礼
売上高として計上する場合、その謝礼金が確実に会社の収益活動によって得られたものであることが重要です。単なる感謝の気持ちとして受け取った謝礼金を売上高として計上すると、不適切な会計処理となる可能性があります。また、売上高として計上する際は、消費税の取り扱いにも注意が必要です。課税事業者の場合、売上高に計上した謝礼金は消費税の課税対象となります。
雑収入
雑収入は、主たる営業活動以外から生じる臨時的な収益を計上する勘定科目です。謝礼金が雑収入として扱われるのは、主に以下のような場合です。
- 業務に直接関係のない協力や助言に対する謝礼
- 偶発的に受け取った謝礼金
雑収入として計上する場合、その謝礼金が会社の通常の事業活動とは関係のない臨時的なものであることがポイントです。定期的に発生する謝礼金や、明らかに業務に関連する謝礼金は、他の適切な勘定科目で処理すべきでしょう。
会社が個人に謝礼金を払ったら源泉徴収は必要か?
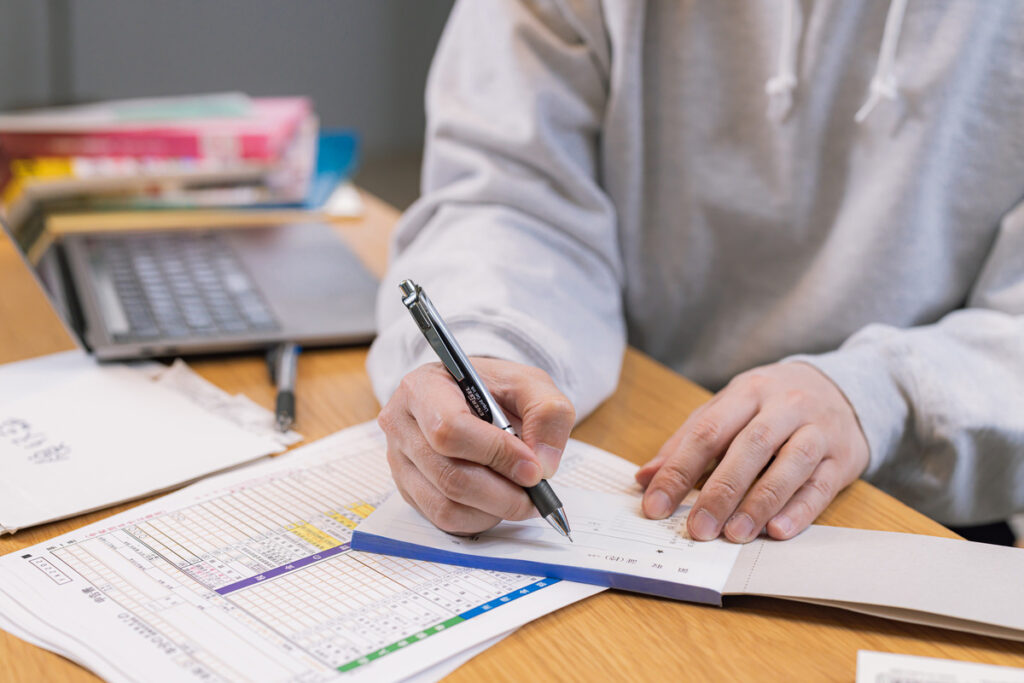
会社が個人に謝礼金を支払う際、源泉徴収は原則として必要です。これは、謝礼金の金額や支払いの理由に関わらず適用されるルールです。多くの企業が見落としがちなポイントですが、適切な処理を行うことで税務上のトラブルを避けられます。
5万円未満でも源泉徴収は必須
5万円未満の謝礼金でも源泉徴収は必要です。例外はごくわずかで、新聞や雑誌への投稿で入賞した方への謝礼など限られたケースのみです。源泉徴収は個人の所得税を効率的に徴収するために必要であり、会社が源泉徴収を行うことで、個人の確定申告の手間を軽減し、税収の安定化を図っています。また、源泉徴収の税率は、支払金額によって異なります。100万円以下の場合は10.21%、100万円を超える部分には20.42%の税率が適用されます。
謝礼金の会計処理方法
謝礼金の会計処理は、その性質によって異なります。一般的には「支払手数料」や「交際費」として処理されることが多いですが、広告宣伝の意味合いが強い場合には「広告宣伝費」として扱うこともあります。
ここでは、10万円の謝礼金を支払う場合の具体的な仕訳例を示します。
- (借方)支払手数料 100,000円
- (貸方)現金 89,790円
- (貸方)預り金 10,210円
この仕訳では、源泉徴収額10,210円(100,000円 × 10.21%)を「預り金」として計上しています。源泉徴収の処理は複雑なため、知識がないとスムーズに対応するのが難しい場合もあります。そこで、おすすめなのが公益情報システム株式会社の「謝金システム」です。
このシステムは、謝礼金の支払い業務を効率化し、源泉徴収の計算や法定調書の作成まで一括で管理できます。また、複数の講師への支払いやインボイス制度への対応といった煩雑な作業も簡素化できる点が大きな特徴です。謝礼金の処理業務をよりスムーズに進めたい場合は、ぜひ「謝金システム」の導入をご検討ください。
会社から個人が謝礼金を受け取る際によくある質問
会社が個人に謝礼金を支払う際、適切な金額設定や税務処理について疑問を抱える担当者は少なくありません。ここでは、企業側が注意すべきポイントについて、よくある質問とその回答を紹介します。
支払う謝礼金の相場はいくらが適切か?
謝礼金の適切な金額は、業界や目的によって大きく異なります。一般的な目安として、以下のような例が挙げられます。
- セミナー講師:1時間あたり1万円~5万円
- 原稿執筆:400字あたり3,000円~1万円
- インタビュー協力:30分あたり3,000円~1万円
ただし、これらはあくまで参考値です。過度に高額な謝礼金は、税務調査の対象となる可能性があります。社会通念上、妥当な金額であることを確認し、必要に応じて稟議書などで金額の根拠を明確にしておくことをおすすめします。
個人に謝礼を支払う場合、消費税の取り扱いはどうなるか?
個人への謝礼金支払いにおける消費税の取り扱いは、以下のように分かれます。
- 事業者でない個人:消費税は課税されず、会社側で消費税分を上乗せして支払う必要はない
- 事業者である個人:免税事業者に消費税分を支払うと仕入控除で不利になる
注意が必要なのは、事業者である個人への支払いです。課税事業者の場合は、支払金額に消費税を上乗せする必要があります。一方で、免税事業者の場合は、消費税の納税義務が免除されるため、支払金額に消費税を上乗せする必要はありませんが、消費税分を支払うと企業としては仕入控除ができないので注意してください。
2023年10月以降、インボイス制度に対応している事業者からの請求書には、適格請求書発行事業者登録番号が記載されています。この場合、消費税の仕入税額控除が可能です。
会社が個人に支払う謝礼金に関するまとめ
謝礼金の支払いは、一見単純に見えて意外と複雑です。しかし、本記事で解説した内容を押さえておけば、適切な処理が可能になります。勘定科目の選択、源泉徴収の実施、消費税の取り扱いなど、重要なポイントを確実に押さえましょう。また、業務効率化を図るなら、公益情報システムの「謝金システム」の導入も検討してみてください。複雑な計算や法定調書の作成を自動化できれば、大きな負担軽減につながるでしょう。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




