大学や専門学校、自治体主催の講座などでの講義に携わる非常勤講師は、専門的な知識や経験を活かして働ける点が魅力です。
しかし、その一方で「非常勤講師の給料はどれくらいなのか」「どのように支払われるのか」「税務処理はどうすればよいか」など、給与に関する疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、非常勤講師の給料に関して基本的な知識から支払い方法、注意点、さらに業務効率化につながるソフトの紹介まで、実務に役立つ情報を丁寧に解説していきます。
これから非常勤講師として働く予定の方はもちろん、講師の採用・給与管理を担当する教育機関の方にも参考になる内容をお届けします。
非常勤講師とは?

非常勤講師とは、大学や専門学校、公的機関が開講する講座などで、常勤(フルタイム)ではなく一定のコマ数・時間数のみ授業を担当する講師のことを指します。授業単位で契約を結ぶケースが多く、勤務形態は週に1~数日、あるいは月に数回とさまざまです。特定の機関に籍を置くことなく、複数の教育機関で教壇に立つ人も珍しくありません。
こうした働き方は、自身の専門性を活かして教育活動に参加できる反面、雇用形態や報酬体系が多様であるため、給与面や社会保険の取り扱いなどで疑問を感じる場面もあります。非常勤講師はあくまでも「業務委託契約」や「非常勤雇用契約」として位置づけられることが多く、常勤職員とは扱いが異なるため、事前にその点を理解しておくことが重要です。
また、近年は文部科学省の方針により、教育の質向上や働き方改革の一環として、非常勤講師の待遇改善や業務の適正化も少しずつ進められています。とはいえ、現場によって対応にばらつきがあるのも実情です。次の章では、実際に非常勤講師として働いた場合の給料水準について詳しく見ていきましょう。
非常勤講師の給料の平均
以下は、非常勤講師の平均的な給料相場をまとめた表です。
| 教育機関の種類 | 1コマあたりの報酬目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 5,000〜7,000円 | 交通費は実費支給が多い |
| 私立大学 | 7,000〜10,000円 | 経験者や専門分野によって上限は高い |
| 専門学校 | 3,000〜8,000円 | 実務経験が重視されることが多い |
| 公共講座(自治体等) | 3,000〜6,000円 | 会場やテーマによって変動が大きい |
非常勤講師の給料は、勤務する教育機関の種類や地域、担当する授業の専門性によって大きく異なります。一般的には、1コマ(90分〜100分程度)の授業あたりで報酬が決まり、その金額はおおよそ3,000円〜12,000円程度が相場です。特に大学や専門学校においては、学部生向けと大学院生向けの講義で単価が異なることもあります。
たとえば、文部科学省や各大学の公開資料をもとにすると、首都圏の私立大学では1コマあたり8,000円〜10,000円という報酬が一般的であり、地方国立大学ではそれよりやや低く、5,000円〜7,000円台に設定されているケースもあります。専門学校や自治体主催の講座などではさらに幅があり、3,000円程度からスタートすることもある一方で、専門性が高いテーマや人気講座では10,000円を超える報酬が設定されることもあります。
さらに、非常勤講師は基本的に時間外手当やボーナスなどが支給されないため、年間を通じた収入は担当コマ数と時給ベースで決まる形になります。仮に1日1コマ・週2日で担当し、1コマ8,000円とすると、月収は約64,000円、年間で約76万円程度です。これを本業とするには物足りないケースもあるため、別の仕事と並行する「兼業非常勤講師」も多く存在します。
非常勤講師の給料が変わるポイント
非常勤講師の給料は一律ではなく、さまざまな条件や評価軸によって金額に差が出ます。以下では、非常勤講師の給料が上下する主なポイントを解説します。これらを理解しておくことで、自身の待遇や今後のキャリア選択に役立てることができるでしょう。
担当する授業内容の専門性
もっとも大きな影響を与えるのは、授業の専門性です。一般的な教養科目よりも、実務経験や高度な資格を要する専門科目のほうが報酬は高くなる傾向があります。たとえば、建築・デザイン・プログラミング・経営など、特定分野の業界知識が求められる講義では、報酬の上限も高く設定されることがあります。
教育機関の種別と地域
大学(国公立・私立)や専門学校など、教育機関の種別によっても給与水準は異なります。一般的には私立大学のほうが報酬単価は高くなる傾向があり、地方よりも都市圏のほうが高めに設定されているケースが多いです。また、交通費の有無や、コマ数に対する割増支給などの規定も機関ごとに異なります。
教育経験や職歴
過去の教育実績や業界でのキャリアも報酬決定の大きな要因です。たとえば、大学での非常勤講師経験が長い方や、業界団体・企業での研修講師を務めた実績がある場合、初回から高めの報酬が提示されることがあります。一方で、講師経験が浅い場合は、まずは相場の範囲内からのスタートとなることが多いです。
勤務頻度と長期性
単発的な講座と、年間通じて継続的に担当する講義では、報酬の安定性が大きく異なります。大学などでは「半期契約」や「年間契約」といった形式がとられることもあり、長期で関わるほうが結果的に1コマあたりの単価が高くなる、もしくは交通費や教材費などの条件が整いやすくなることもあります。
授業以外の業務負担
近年では、非常勤講師にもシラバス作成、試験・レポート採点、学生対応などが求められる場面が増えています。これらの業務にどれだけ時間がかかるか、報酬に含まれているか否かは、契約の条件に大きく左右されます。業務負担が大きいにもかかわらず、報酬が授業時間分のみである場合、実質的な時給は下がってしまいます。
非常勤講師の給料の支払い方法
非常勤講師の給料は、常勤職員と異なり、その雇用形態や契約内容によって支払い方法が多様になります。大学や公的機関における講師報酬は、月給制ではなく、原則として「1コマ単位の報酬」として支払われる形式が主流です。そのため、講義の実施回数や勤務月によって、受け取る金額は毎月変動するのが特徴です。
振込時期と形式
多くの教育機関では、講義が実施された月の翌月または翌々月に報酬が銀行振込で支払われます。たとえば、4月に開講した授業の報酬が5月末や6月初旬に支払われるといったサイクルです。これは、講義実施報告書の提出や、授業確認の手続きが完了してから支払いが確定するためです。
また、支払いのタイミングは学期末にまとめて行われることもあります。特に非常勤講師が複数の授業を担当している場合、機関によっては「半期分まとめて支払う」といった形式を採用することもあります。
契約形態による違い
非常勤講師の報酬は、雇用契約としての「給与」として扱われる場合と、「報酬・謝金」として扱われる場合があります。前者の場合は所得税や社会保険が給与と同様の扱いになりますが、後者の場合は「支払調書」が発行され、税務上の取り扱いが異なります。
特に、「報酬・謝金」として支払われる場合、源泉徴収の対象となり、一定金額以上になると確定申告が必要になるため、講師自身が納税管理を行う必要があります。
公的機関・大学の管理方法
多くの公立大学や自治体関連機関では、講師への支払いを円滑に行うため、事前に登録された口座情報・マイナンバー・契約書類に基づき、支払いデータを管理しています。また、講師自身が講義終了後に「勤務報告書」「出講確認書」などの書類を提出することで、報酬支払が確定するという流れが一般的です。
こうした支払い処理は、講師数が多い場合や、講義数が多い場合、事務側にとっても煩雑な業務となりやすいため、次章で紹介するような専用の管理ソフトを活用するケースも増えています。
非常勤講師の給料で注意すること
非常勤講師の給料は、金額面だけでなく「支払方法」や「税務処理」においても注意すべきポイントがいくつか存在します。特に、報酬を「給与」ではなく「謝金」として受け取る場合、事務処理や税務上の扱いに細かな違いが出てくるため、事前に正しく理解しておくことが重要です。
支払調書の発行と税務申告
非常勤講師の報酬が「謝金」として支払われる場合、その金額が年間で5万円を超えると、支払者である教育機関などは税務署に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する義務があります。また、受け取る講師側にもこの支払調書の写しが渡され、これをもとに確定申告を行う必要があります。
この支払調書は、給与所得とは異なり、原則として「雑所得」または「事業所得」として扱われ、他に給与収入や年金収入などがある場合は合算して申告を行います。なお、源泉徴収されている場合でも、他に収入がある方や一定額を超える方は確定申告が必要になることがあります。
経費の取り扱い
講師として活動するにあたってかかる費用(交通費、教材作成費、資料購入費など)は、雑所得や事業所得として計上する場合、確定申告時に経費として差し引くことができます。ただし、領収書の保管や業務上の必要性を明確にすることが求められます。申告の際に必要になるケースがあるため、授業準備のための支出はしっかり管理しておきましょう。
所得税の源泉徴収
講師報酬は、源泉徴収の対象となるため、支払時に一定の割合で税金が差し引かれます。たとえば、1回の支払金額が10万円以下であれば10.21%、10万円超であれば20.42%の源泉所得税が控除されるというのが一般的な仕組みです。支払明細で「控除前の金額」と「源泉徴収税額」「振込額」を確認するようにしましょう。
支払遅延や確認漏れに注意
非常勤講師の報酬は、講義報告や出勤記録の提出が正しく行われていない場合、支払が遅れることがあります。特に公的機関では、厳密な手続きが必要となるため、指示された提出期限や記載方法を守ることが求められます。また、マイナンバーや口座情報の不備も支払い遅延の原因になりやすいため、初回の契約時には正確な情報を提出することが大切です。
非常勤講師の給料の支払いに便利なソフト
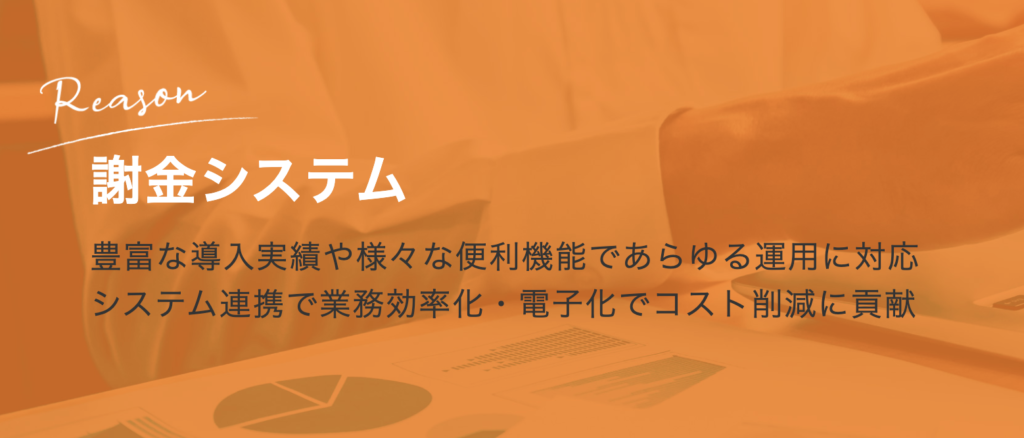
非常勤講師への報酬支払は、出講管理・支払条件の設定・源泉徴収計算・支払調書の作成など、非常に手間がかかる作業です。とくに講師数が多くなると、表計算ソフトだけでの管理には限界があり、ミスや遅延のリスクも高まります。そこで導入を検討したいのが、講師謝金の支払いに特化した専用ソフト「謝金システム」です。
「謝金システム」はクラウド型の業務支援ツールで、講師の出講情報から謝金計算・源泉徴収の控除処理、支払調書の電子出力までを一元的に行うことができます。特に公益法人や大学、行政委託講座などで導入実績が多く、定型的な業務の効率化とヒューマンエラーの削減に貢献しています。
たとえば、非常勤講師の講義回数や支払条件をシステムに登録しておけば、年度末に面倒な支払調書の作成も自動的に対応できます。また、源泉徴収税額の自動計算や、複数講師の一括支払明細出力、マイナンバーの安全な管理にも対応しており、法令順守の観点でも安心です。
実際の運用においても、支払データのCSV出力や銀行への一括送信フォーマット出力など、会計部門との連携も取りやすく、業務全体のスリム化が可能です。年に数回しか講義がない非常勤講師に対しても、漏れのない支払いが行える点は、教育機関の信用維持にもつながります。
教育機関や団体で非常勤講師を多数抱えている場合には、謝金システムを活用することで、担当者の業務負担を軽減し、より透明性の高い報酬管理を実現することができるでしょう。
非常勤講師の給料についてまとめ
講師報酬は「給与」ではなく「謝金」として支払われるケースも多く、その場合は源泉徴収や確定申告、支払調書の発行といった税務上の手続きが必要です。支払金額に見合った準備時間や業務負担を考慮することも、非常勤講師として安定して働き続けるうえで重要な視点となります。
教育機関の担当者にとっても、講師への謝金支払業務は細かく煩雑な作業が多く、法令順守やスムーズな処理が求められます。そうした課題に対して、公益情報システムの「謝金システム」のような専用ソフトを導入すれば、支払処理の自動化や支払調書の作成ミス削減に大きく貢献します。
非常勤講師として働く方、またその支払い業務に携わる教育機関の方は、本記事で紹介した内容をもとに、自身に合った管理方法や支払体制を見直してみてはいかがでしょうか。より安心して講師業務に専念できる環境づくりの一助となれば幸いです。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




