テレビやインターネットなどで電子帳簿保存法が改正されて義務化されるといったニュースを見聞きしたことがあるという方も、多いのではないでしょうか。電子帳簿保存法とは、請求書や見積書などの書類をデータで保存する法律のことです。2022年1月に改正・義務化されており、会社を持つ経営者は必ず知っておかないといけない内容です。そこで本記事では、改正された電子帳簿保存法の概要や義務化のタイミング、改正後の対応方法、おすすめのソフトについて解説します。
電子帳簿保存法の改正とは

電子帳簿保存法とは、保存が義務付けられている帳簿や領収証、請求書といった様々な書類を電子データとして保存する際に遵守が必要な法律です。かつては帳簿類は紙で作成して保存するというのが当たり前とされていましたが、コンピューターの普及によって電子データによる管理への移行が求められるようになりました。
2022年1月から、電子帳簿保存法は改正・義務化されており、多くの会社で周知が必要な法律となっています。、義務化された背景には、データの信頼性を確保するために電子化にあたっての必要な要件を定める目的が挙げられています。
電子帳簿保存法が改正・義務化されたタイミング

2022年1月以後、電子帳簿保存法は義務化されました。義務化に伴い、電子取引情報を電子情報のまま保存が必要になりました。これまでも電子取引に関するデータについては、電子データとして保存するというのが原則でしたが、例外的に書面で出力して保存することも可とされていました。しかしながら、2022年1月以後の改正によって紙での保存は認められなくなり、必ず電子データで保存しなければならなくなったのです。
帳簿書類を電子データとして保存する場合に必要であった検索項目が削減されて、「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目のみへと変更されるといった規制緩和も行われています。そのほかにも、データやスキャナ保存における税務署長の事前承認の手続きが廃止されたり、スキャナ保存時のタイムスタンプの付与期間が3営業日以内から最長約2ヶ月と概ね7営業日以内へと延長されるといった措置も講じられています。そのため、2022年1月以降の義務化によって、ルールが厳格化されたという訳ではありません。
電子帳簿保存法の改正・義務化に必要な対象書類
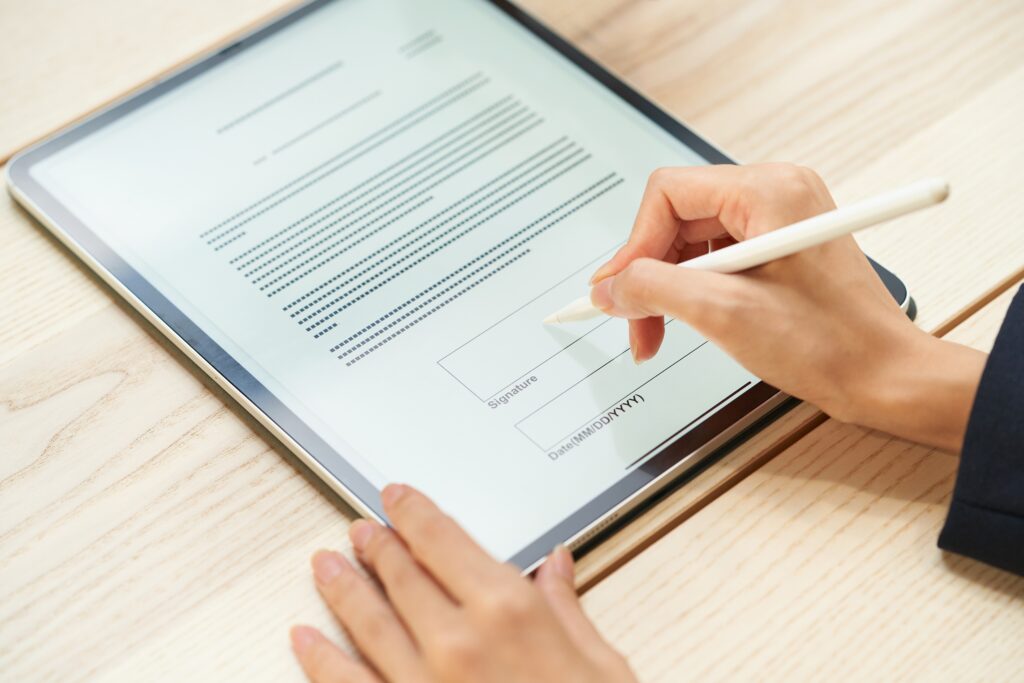
電子帳簿保存法の対象書類は、「電子取引のデータ保存時」「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存時」「スキャナ保存時」によって異なります。保存対象の区分によって異なるため、それぞれ対象区分ごとの対象書類を確認する必要があります。
電子取引のデータ保存時
電子取引のデータ保存時には、請求書や見積書、納品書などの書類が必要です。自社が関連する書類はすべて保存対象になります。データ保存で統一している会社の場合、スキャナ保存や別途データで送付してもらう形で保存することになります。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存時
国税関係帳簿書類では、データや紙で残っている税務申告で使用する決算関係書類や取引関係書類が該当します。仕訳帳や総勘定元帳、損益計算書などが該当します。国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の対象文書については、データ保存が義務ではありません。紙で保存する場合は、一定の要件を満たす必要がありますが、紙での保存も可能です。
スキャナ保存時
スキャナ保存時の対象書類は、取引会社と紙でやり取りした内容が対象になります。主に、紙ベースの請求書や見積書、納品書が該当します。スキャナ保存は義務付けられているわけではないため、紙のまま保存しても問題ありません。ただ、会社によってはデータ保存で統一する場合もあるので、その場合は電子帳簿保存法の要件に沿った保存が求められます。
電子帳簿保存法改正の義務化に違反した場合のペナルティ
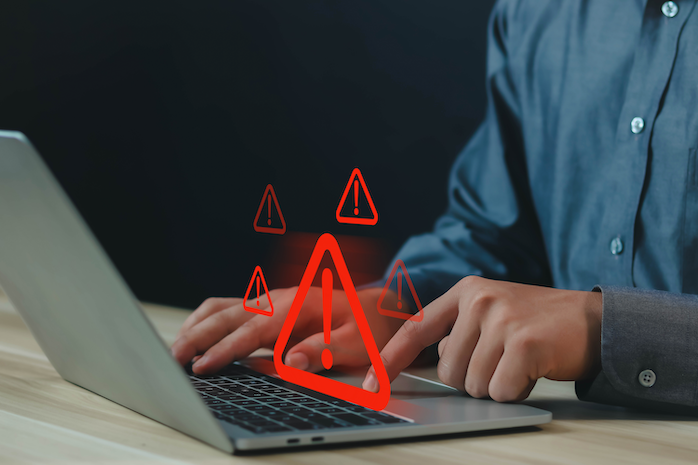
電子帳簿保存法に対応しない場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。
- 青色申告承認の取り消し
- 追徴課税
- 会社法による過料の徴収
電子帳簿保存法の場合、要件を満たさず、かつ書類を保存しなかった場合には会社法に違反します。100万円以下の罰金を科せられる場合もあるため、電子帳簿保存法は遵守するようにしましょう。
電子帳簿保存法の改正・義務化に対応する方法

義務化された電子帳簿保存法に対応するためにも、以下の4つを押さえておく必要があります。
- 対応方法①:自社の電子取引状況を把握する
- 対応方法②:電子取引におけるデータ保存の要件を確認
- 対応方法③:データ保存の場所を社内共有する
- 対応方法④:専用システム・ソフトを使用し、社内システムを整備する
1つずつ順番に紹介していきます。
対応方法①:自社の電子取引状況を把握する
まずは、自社でどのような電子取引が行われているのかを把握しましょう。具体的な電子取引として、メールでの請求書や納品書のやり取り、Webページからダウンロードした領収書などが該当します。自社の電子取引状況を把握することで、保存すべき書類を明らかにできます。
対応方法②:電子取引におけるデータ保存の要件を確認
電子帳簿保存法におけるデータ保存の要件を確認しておくことも大切です。データ保存の要件では、正確なデータ保存と必要なデータをすぐに見つけられる可視性が挙げられます。2つの要件を確認し、それらを満たすことができる保存方法やシステムの利用を検討する必要があります。
対応方法③:データ保存の場所を社内共有する
要件確認後はデータ保存の場所を決定し、社内に共有します。たとえば、税務調査がくると、保存したデータのダウンロードやプリントアウトが求められる場合があります。社内で共有しておかないと、提示を求められたときに対応ができません。
データは社内の誰が見ても分かる箇所で管理・保存しておくことが大切です。保存する際、パソコンに保存するとデータが飛んでしまう可能性もあるため、クラウド上で管理するのが安心です。
対応方法④:専用システム・ソフトを使用し、社内システムを整備する
データの保存先・保存方法が決まれば、システムやソフトを使用することを視野に入れましょう。電子帳簿保存法に対応しているシステムやソフトを使用することによって、一元してまとめることができ、間違いを無くすことができます。場合によっては、先述した「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存時」「スキャナ保存時」などの保存方法もあります。自社に合ったシステムを使用し、電子帳簿保存法に対応していきましょう。
電子帳簿保存法の改正・義務化に対応している会計ソフト3選

電子帳簿保存法に伴い、帳簿に関する書類がデータ化されました。電子眺望保存法の義務化に伴い、、データ保存が簡単にできる会計ソフトが重宝されています。ここからは、電子帳簿保存法の改正に対応している代表的な会計ソフトを3つ紹介します。
マネーフォワードクラウド会計
マネーフォワードは経理や会計、経費精算、勤怠管理等の様々なクラウドツールを提供しています。マネーフォワードクラウド会計は、同社が提供している会計ソフトで、バックオフィス全体の業務効率化が実現可能です。改正後の電子帳簿保存法にも対応しているため、データの保存に悩んでいる会社にも役立ちます。
マネーフォワードクラウド会計は、取引先などから受け取ったPDFなどの電子データを、法定要件を満たした「マネーフォワード クラウドBox」で自動保存ができます。余計な手間をかけずに改正電子帳簿保存法に対応できるため、業務に支障が発生しません。他のツールと連携すれば、資金を一元的に管理できるようになるというのも魅力的なポイントです。
freee会計
freee会計は、初心者にも分かりやすく、会計に不慣れな人でも簡単に使いこなせます。会計の知識が不足しているスタートアップをはじめとする中小企業や個人事業主などの間で高い人気を有しています。
請求書や見積書をはじめとする取引書類の管理に加えて、帳簿の作成についてもソフトを使って一貫した管理が可能です。漏また、「優良な電子帳簿」の要件を満たしているため、万が一税務署への申告漏れがあった時でも、過少申告加算税を5%軽減してもらえます。
WEBバランスマン
WEBバランスマンは、公益法人におすすめの会計ソフトです。簿記の知識があまりない人でも簡単に入力できるデザインになっているほか、2016年と2020年の両方の会計基準に対応した決算書を出力することが可能です。
また、会計に関する情報が自動的にアップデートされる仕様になっているため、常に最新の公益法人会計基準を導入できるというのも嬉しいポイントです電子帳簿保存法の電子化の要件も満たしているので、WEBバランスマンを導入しておけば、義務化への対応も十分に可能です。
電子帳簿保存法の改正・義務化をしっかりと理解しよう

電子帳簿保存法の改正によって、多くの企業が電子データによる保存が義務化されました。そのため、自社内で経理・会計に携わる人はもちろん、その他の従業員も電子帳簿保存法に関する要件を確認しておく必要があります。電子帳簿保存法で重要なのは、保存法です。改正法に対応した会計ソフトを導入することで、安心・安全にクラウド上でデータを保存できます。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




