この記事では「電子帳簿」をテーマに、仕組みや改正内容、注意点をわかりやすく解説していきます。
近年、企業の会計や税務においてデジタル化が急速に進み、電子帳簿保存法や電子取引制度といった関連法令への対応が欠かせなくなっています。紙の帳簿管理と異なり、電子的に処理・保存することには多くの利点がある一方、正しいルールを理解しなければトラブルにつながることもあります。
この記事を読むことで、電子帳簿の基本から法改正のポイント、実際に活用できるソフトまで体系的に理解することができるでしょう。特に公益法人や非営利団体に向けては、専用の会計ソフト「WEBバランスマン」についても触れますので、ぜひ最後までご覧ください。
電子帳簿とは?
電子帳簿とは、これまで紙で作成・保存していた会計帳簿や仕訳帳、総勘定元帳などを、電子データとして作成・保存するものを指します。国税関係帳簿として認められるためには、国税庁が定める「電子帳簿保存法」に準拠することが必須です。
従来は帳簿を紙に印刷して製本し、保管義務期間である7年間(法人によっては10年間)を倉庫やキャビネットで管理していました。しかし、近年は企業のDX化や業務効率化の観点から、電子的に記録しそのまま保存する仕組みが普及してきています。
電子帳簿は単なるPDF化やスキャンデータ保存ではなく、作成したデータを適切なシステム上で管理し、改ざん防止や検索機能が担保されている必要があります。この点を満たすことで、国税庁から正式に「電子帳簿」として認められるのです。
電子帳簿の導入は、単に紙の削減にとどまらず、バックオフィス業務全体のデジタル化を推進する重要な一歩となっています。
電子帳簿保存法の対象書類と対象ではない書類
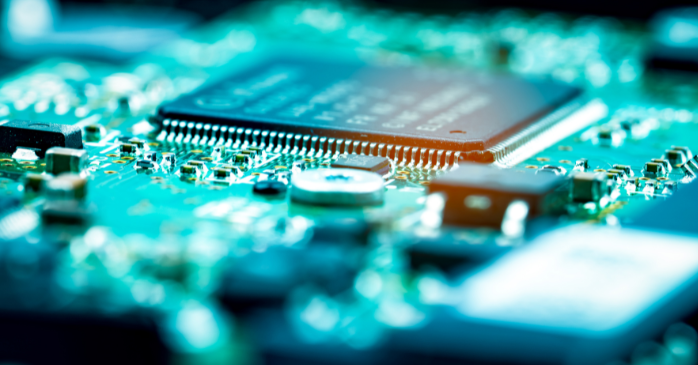
電子帳簿保存法の対象書類と対象ではない書類について、以下の表にまとめました。
| 区分 | 書類の種類 | 具体例 | 保存方法 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 国税関係帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳 | 電子帳簿保存 |
| 対象 | 決算関係書類 | 貸借対照表、損益計算書 | 電子帳簿保存 |
| 対象 | 取引関係書類(自社作成分) | 請求書、発注書、納品書の控え | 電子帳簿保存 |
| 対象 | 取引関係書類(受領分) | 領収書、請求書、契約書 | スキャナ保存 |
| 対象 | 電子取引データ | 電子メールでの請求書、クラウド請求システムのデータ | 電子データ保存 |
| 対象外 | 手書きの主要簿 | 手書きで作成した総勘定元帳、仕訳帳 | 紙の原本保存が必要 |
| 対象外 | 手書きの取引関係書類 | 手書きで作成した請求書、見積書 | 紙の原本保存が必要 |
| 対象外 | 手書きの補助簿 | 手書きで作成した補助簿 | 紙の原本保存が必要 |
| 対象外 | 上記をスキャナ保存したもの | 手書き書類をスキャンしたデータ | 無効(紙原本保存必須) |
対象書類:帳簿・国税関係書類
電子帳簿保存法では、企業や個人事業主が作成・保存する多くの帳簿や国税関係書類が対象となります。
具体的には、会計上必ず作成する仕訳帳や総勘定元帳などの「国税関係帳簿」、決算時に必要となる貸借対照表や損益計算書などの「決算関係書類」、さらに日常の取引に伴い発生する領収書や請求書、見積書、発注書などの「取引関係書類」が含まれます。自社が作成した請求書や納品書などは電子帳簿保存の対象となり、相手方から受領した領収書や請求書はスキャナ保存によって対応が求められます。
また、電子メールによる請求データや、クラウドサービス経由で受領した請求書などは「電子取引データ」とされ、電子的に保存しなければなりません。このように、対象範囲は多岐にわたり、紙から電子データまで幅広く管理が求められるのが特徴です。
対象とならない書類:帳簿・国税関係書類
一方で、すべての帳簿や書類が電子帳簿保存法の対象となるわけではありません。
とくに、手書きで作成した帳簿や補助的な書類は、法的には電子保存の対象外です。例えば、手書きで記帳した総勘定元帳や仕訳帳といった「主要簿」、また手書きで作成した請求書、見積書、補助簿などは電子保存の認定を受けられず、紙のまま保存しなければならないとされています。
これらの書類をスキャナで取り込みデータ化したとしても、電子帳簿保存法の保存要件を満たさず、法令上は有効な保存方法とみなされません。そのため、会計処理や税務調査の際には紙の原本を提示できるように管理することが必要です。
つまり、すべてを電子化すれば良いというわけではなく、手書き文書に関しては引き続き原本管理を行う必要がある点が大きな注意点となります。
電子帳簿の改正内容

電子帳簿保存法は、1998年に制定されて以来、デジタル化の進展に合わせて何度も改正されてきました。特に2022年1月の改正は大きな転換点であり、企業や個人事業主に大きな影響を与えています。ここでは、近年の改正内容を整理して解説します。
事前承認制度の廃止
以前は、電子帳簿を導入する際に税務署長への「事前承認申請」が必要でした。しかし、2022年1月以降はこの制度が廃止され、申請なしで電子帳簿を運用できるようになりました。これにより、電子化をスムーズに始められるようになり、企業の負担軽減につながっています。
スキャナ保存要件の緩和
紙の請求書や領収書をスキャナで読み取って保存する「スキャナ保存」についても、改正により要件が緩和されました。具体的には、定期的な「相互けん制」や「定期検査」の義務が撤廃され、スマートフォンでの撮影データも正式に認められました。これにより、出張先や自宅からでも簡単にデータ化できる環境が整いました。
電子取引データ保存の義務化
最も大きな改正点は、電子取引データの保存が義務化されたことです。従来は、電子メールで受け取った請求書やクラウド上で発行された領収書を印刷して紙で保存しても認められていました。しかし、改正後はこれらを必ず電子データのまま保存する必要があります。紙保存は認められず、システム上で改ざん防止や検索性を確保することが求められるようになりました。
猶予措置と段階的適用
急な完全義務化に対応できない事業者も多かったため、猶予措置が設けられています。2023年12月末までは宥恕措置が適用され、保存方法が不十分でも直ちに罰則を受けることはありませんでした。ただし、2024年1月からは原則として電子取引データの電子保存が必須となっています。
このように、電子帳簿に関する法改正は単なるデジタル推進ではなく、企業のコンプライアンスや業務効率化に直結する重要な内容を含んでいます。ここまでを理解したうえで、次に電子帳簿に対応できるソフトを見ていきましょう。
電子帳簿に対応できるソフト3選

電子帳簿保存法への対応は、法律を理解するだけでは不十分で、実際に帳簿や書類を適切に保存できる環境を整える必要があります。そのために欠かせないのが、法令要件を満たした会計ソフトや文書管理システムです。ここでは、実際に導入が進んでいる代表的なソフトを3つ紹介します。
弥生会計オンライン
中小企業や個人事業主の利用者が多い「弥生会計オンライン」は、電子帳簿保存法に完全対応した会計ソフトです。電子取引データを自動で取り込み、検索性や真実性を確保した形で保存できます。クラウド型のため、インターネット環境があればどこからでも利用できる点も魅力です。法改正に対応するためのアップデートも迅速に提供されており、安心して利用できます。
マネーフォワードクラウド会計
マネーフォワードクラウド会計は、電子帳簿保存法の要件を満たす機能を標準で備えています。領収書や請求書をスマートフォンで撮影し、そのままクラウドにアップロードして保存可能です。また、電子取引データの検索やタイムスタンプ付与なども自動処理されるため、担当者の手間を大幅に削減できます。経理と経営管理を一元化できる点も評価されています。
WEBバランスマン
公益法人や学校法人など、一般企業とは異なる会計基準を求められる団体におすすめなのが「WEBバランスマン」です。公益法人会計に準拠しているだけでなく、電子帳簿保存法にも対応しているため、法改正後も安心して運用できます。特に公益法人は監査対応が厳格であるため、法令要件を満たしたシステムを導入することが不可欠です。WEBバランスマンは、そうしたニーズに応えた専門性の高いソフトといえるでしょう。
電帳法で注意すること

電帳法(電子帳簿保存法)に対応する際には、単にソフトを導入すれば良いというわけではなく、運用面での注意が欠かせません。要件を正しく理解し、組織全体で遵守できる仕組みを整えることが重要です。ここでは特に注意すべきポイントを解説します。
真実性と可視性を確保する仕組み
電子帳簿は、改ざんされていないことを担保する仕組みが求められます。タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムを利用することが必須です。また、監査や税務調査時に速やかにデータを提示できるよう、保存形式やアクセス権限の管理を徹底しなければなりません。
検索性の確保
電帳法では、取引年月日や金額、取引先といった項目を検索できることが要件のひとつです。これを満たしていない場合、電子帳簿として認められず、法的に無効となる可能性があります。そのため、保存時に正しいインデックスを付与し、後から容易に検索できる体制を整える必要があります。
紙と電子の使い分け
法改正により電子取引データは電子保存が義務化されましたが、帳簿や一部の書類については依然として紙での保存が認められるケースもあります。どの書類が電子保存の対象かを整理し、誤って紙に出力して保管してしまうと違反になることもあるため注意が必要です。
社内ルールの整備
電帳法対応ソフトを導入しても、社員が正しく運用できなければ意味がありません。例えば、領収書を受け取った場合の処理フローや、電子データのアップロード期限を社内規程として明文化しておくことが求められます。定期的な研修を実施してルールを浸透させることも有効です。
法改正への継続的な対応
電子帳簿保存法は近年、頻繁に改正が行われています。今後も規制や要件が変化する可能性が高いため、常に最新の情報を収集し、ソフトや運用体制を見直す必要があります。ベンダーによるアップデートが迅速に行われるかどうかも、ソフト選びの大きな判断基準となります。
電帳法についてまとめ
電帳法(電子帳簿保存法)は、企業や団体が取引データを電子的に保存・管理するための重要な法律です。なぜ「電帳法」と略されるのかといえば、「電子帳簿保存法」の頭文字を取った呼び方であり、実務の場で広く使われています。法改正を経て、電子取引データの保存が義務化されるなど、企業にとって対応は避けて通れない課題となりました。
電帳法の基本内容は、真実性と可視性を担保し、検索性を確保した上で電子帳簿を保存することです。2022年以降の改正では、スキャナ保存や電子取引における要件が大きく緩和されつつも、電子取引データは紙保存では認められず電子保存が必須となっています。このため、従来の紙中心の業務フローを見直し、効率的に電子化できる体制を整えることが求められます。
対応を進めるうえで役立つのが専用のソフトです。例えば公益法人向けの「WEBバランスマン」のように電帳法対応を支援するシステムを活用すれば、保存要件を満たしつつ業務効率を高めることができます。他にも市販の会計ソフトやクラウド型システムなど、多様な選択肢が存在します。自社の業務規模や体制に合わせて選ぶことが大切です。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




