謝礼の領収書は、法人が経理処理をする上で必要な書類です。しかし、領収書のルールや書き方を知らなければ、講師にそれを指定して書かせることはできません。
そこで、法人向けに謝礼の領収書の基本を押えた上で、有効な領収書の作成ルールや項目の書き方を紹介します。
謝礼の領収書とは
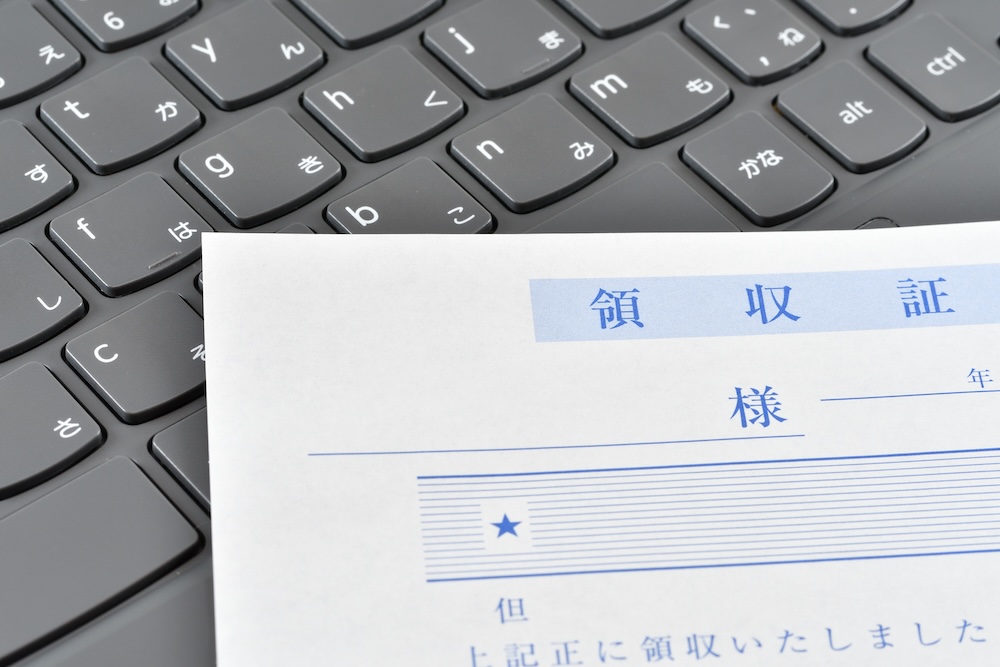
謝礼の領収書とは、謝礼を渡した際に相手から発行される書類を指します。この謝礼とは、相手に感謝を伝える気持ちとして渡すお金や物品のことです。「謝礼」の呼び方以外に、「謝金」や「謝礼金」などがあります。
渡す相手は、講演会や研修、セミナーに協力してもらった講師や、専門的なアドバイスを受けた場合の大学教授や専門家などです。
そして、謝礼は基本的に「感謝の気持ちを形にしたもの」です。例えば、相手にお礼として現金を3万円渡す場合は謝礼の扱いです。謝礼の領収書には、3万円を受け取ったことを証明する記載や印などを求めます。
しかし、謝礼が現金である必要はなく、講師や協力者に感謝が伝わるなら、それが「謝礼」です。金銭以外は、以下のような金券や物品がよく渡されています。
・商品券、ギフトカード
・自社製品やサービス
・食品、飲料(菓子折りやお茶・コーヒーセットなど)
・チケット、招待券
謝礼の領収書の守るべきルール
謝礼の領収書には、受け取るタイミングや経費区分など守るべきルールがあります。以下に、ルールの詳細を説明します。
謝礼の領収書を受け取るタイミング
謝礼には、事前に渡すことが決まっている場合と、予定外に追加で渡す場合があります。その際に、領収書は謝礼を受け取った講師や協力者側に請求します。領収書を必要とする企業や公益法人は、原則、経理処理に領収書を必要とするため、謝礼を渡すのと同時に領収書の受取りが必要です。
ただし、謝礼の領収書は、事前に用意がないことも少なくありません。特に、予定外に追加で渡す場合などは領収書の準備ができません。そのため、領収書の作成ができるまで待って渡すか、銀行振込など振込の事実が確認できる書類で代替できる方法か、いずれかにします。すぐに現金手渡しが不可欠な場合は、先方に領収書の用意を事前に要請することです。
謝礼の領収書における経費処理の区分
謝礼の領収書は、経理処理の区分で「領収書」(証憑・支出証明書)扱いで分類されます。勘定科目とは別に仕分けを行い、「報酬や対価を含まない謝礼」と認められる領収書はそのまま謝金の区分で処理される仕組みです。
そのため、領収書は会計上の1つの区分(請求書や借用書と区別するもの)です。勘定項目は、謝礼が実際に「謝金」の区分が基本ですが、対価や報酬に当たる場合は、「外注費」や「講師料」の科目に計上します。
また、経費処理の区分に関連して、事業として受け取る場合(法人)は消費税が非課税とならず計算・記載が必要です。さらに、金額が大きい場合や繰り返し謝礼を渡す場合は、源泉徴収を必要とします。
・10万円を超える
・繰り返し謝礼を渡す(月数回など)
・原稿料や講演料として渡す
・謝礼は名ばかりで、専門職や士業に支払う報酬に当たる
上記は、源泉徴収が必要となる場合の例です。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
謝礼の領収書に必要な5つの項目の書き方

謝礼の領収書には、書き方に一定のルールがあります。特に、誰が作成しても日付、宛名、金額、但し書き、発行者の5つの項目を正しく記入することが必要です。そこで、5つの具体的な書き方や項目ごとのポイントを解説します。
日付
領収書に記載する日付は、原則、実際に金銭や物品を渡した日とします。事前に約束していた場合でも、その支払日を明確に書くことです。例えば、講演後に謝礼を手渡したならその当日を記入します。
振込による支払いの場合は、口座に着金した日を用いるのが一般的です。渡す前に日付を作成して渡す行為は、架空の領収書として不正とみなされることがあります。
宛名
宛名には謝礼を受け取った相手の氏名や所属を正確に記載します。法人に対して謝礼を支払った場合は会社名や団体名を、個人に渡した場合は「本名+様」を記入します。一般的に「上様」の表現は使わず、略称ではない正式な宛名で「会社名・団体名+御中」を用いることです。
金額
金額は数字を明確に書き、改ざん防止のために頭に「金」を付け、末尾に「也」と入れる書き方がよく用いられます。例えば、「金三万円也」と記せば、後から数字を書き足すことを防げます。
また、算用数字で「¥30,000-」とするか、同時併記をすれば、それが実務上ではわかりやすい書き方です。謝礼は数千円から数万円と幅があり、税込み(税抜き)記載の金額で記録する必要があります。税務処理に用いる書類であるため、端数処理や曖昧な表記を避け、実際に支払った金額をそのまま書くことがおすすめです。
但し書き(受領事由)
但し書きには、「謝礼を支払った理由」を明確に記入します。例えば、年月日をつけて、その上で「取材協力謝礼として」「講演会の謝礼として」「原稿執筆料として」など、具体的な内容を記載することです。
単に「謝礼」とだけ書くに留めると、経費区分が不明確になり、後の確認作業に支障をきたします。また、理由を明確に書くことで、経理処理の勘定科目を判断しやすくなります。実務では、但し書きの記載内容が不十分な領収書は不備と見なされることがあるため注意が必要です。
発行者
発行者には謝礼を受け取った人の氏名や所属を記載します。個人であれば自筆の署名・捺印、法人であれば会社名と代表者名(担当者名)、さらに角印を押すことです。
謝礼の領収書を書くときのコツ(テンプレートあり)
謝礼の領収書を作成する際は、記載漏れや誤記を防ぐことです。特に日付や金額、但し書きは間違いやすいため、ポイントを押えて書くことが求められます。
令和5年9月15日 受領書
〇〇株式会社御中
金 32,400円也 (※実際受け取った金額)
但し 令和5年9月10日 講義料 36,000円(税込)
(源泉所得税額 3,600円控除後)
発行者:山田 太郎(署名) 収入印紙(必要な場合のみ)
上記の例を参考に、項目のポイントを押えて書くことで大体のミスを防げます。領収書は法律で項目が決まっているわけではないため、講師や法人によって、項目の細かい部分が違うケースもあります。あくまでも、上記のテンプレートは税務上で認められやすい最低限を満たしたものです。
また、訂正が必要な場合は二重線を引いて訂正印を押すのが基本です。修正液や書き直しは不適切とされるため注意が必要となります。
字は客観的に読みやすくすることです。その上で、理由を書く際には、ストレートに誤解を招かない表現を心掛けることが実務上のポイントです。
電子領収書の場合のルール
電子領収書は紙の領収書と同様に、日付、宛名、金額、但し書き、発行者を記載する必要があります。紙との違いは、電子帳簿保存法によって印鑑ではなく電子署名やシステム上の承認を利用する点です。
電子領収書を保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たすことが求められます。具体的には、改ざん防止の仕組みを備えた形式で保存することが求められます。例えば、PDFにタイムスタンプを付与したり、会計ソフトの発行機能を利用したりする方法です。電子領収書も経理処理や税務申告に用いることができます。
収入印紙は基本的にいらない
謝礼に関する領収書は、収入印紙の貼付が必要ありません。印紙税は国税庁が取り決めた「営業上の取引」で金銭を受け取った場合に課されるものです。
そのため、講師謝礼などに支払った金銭は、領収書を発行しても印紙税の対象から外れます。ただし、謝礼の名目であっても実態が業務委託契約と同じである場合や領収書の範疇を超えて5万円以上の支払書類となる場合は課税の対象です。
謝礼の領収書におすすめな「謝金システム」
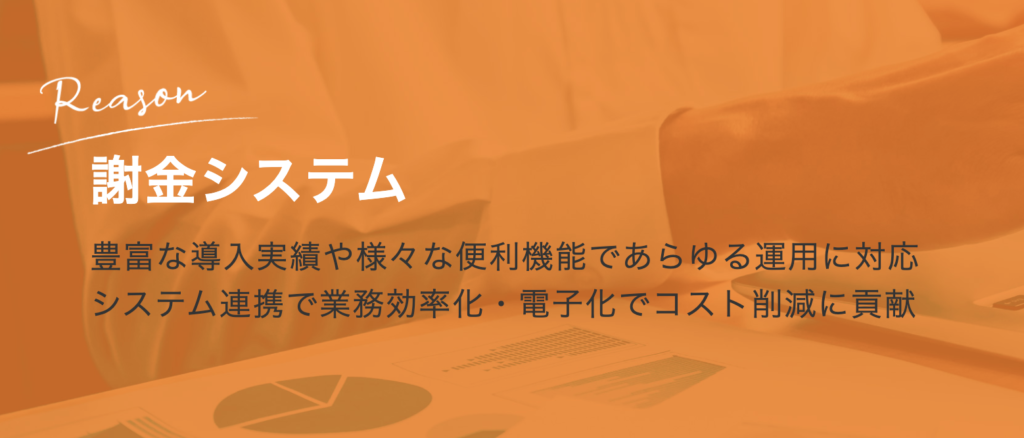
謝礼の領収書を作成するときにおすすめなのが公益情報システムの「謝金システム」です。公益法人はもちろんのこと、一般法人でも領収書作成や会計処理に使えるのが特徴です。
特に講師への謝礼金や、臨時職員への報酬の支払いに対応しています。1つの画面に入力するだけで、消費税や源泉徴収税の計算などの会計処理を短縮。同じ項目への再入力も不要です。
講師マイページを通じて謝金を渡した側が発行する「謝金明細書」をクラウド共有でも配信できます。そのため、書類郵送のコスト負担や手間もかかりません。特に口座振込の場合は、入金の証明書類が領収書の役割を果たすため、即座に領収書を発行して経理処理で使用することが可能です。
謝礼の領収書の書き方のまとめ
謝礼の領収書は、謝礼の支払いを証明する書類です。受け取った講師側が作成したものを受け取る必要があります。書くときのルールは日付、宛名、金額、但し書き、発行者を記載し、領収書としての要件を満たすことが大事です。ただし、口座振込の場合は、送金の証明書類や明細がそのまま領収書の代わりを果たします。以上を踏まえて、謝礼の領収書を正しく扱って、経理処理に使うことです。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




