支払調書の作成は、事業者や企業にとって税法上の作成義務となる書類の1つです。しかし、作成した書類を発行して、それを交付・提出するかどうかは、送る相手により異なります
また、郵送が可能かどうかは、書類の枚数とその提出方法によって変わることです。
そこで本記事は、支払調書を郵送する場合の相手を「支払い相手」と「税務署」で区別して、それぞれ郵送の可否や義務の有無を解説します。
支払調書の郵送は支払い相手に必要であるか

結論から述べれば、支払調書の支払い相手(受取人)への郵送は法律上、義務ではありません。
この支払調書とは、報酬や料金、契約金などの支払い情報を税務署に報告するための書類です。そのため、支払い相手に発行してそれを提示するケースや、郵送して現物を手元に届けるケースでは、支払調書を作成した側が渡す方法を自己判断により任意で行うものとなります。
支払調書と源泉徴収票で違う
この点で、給与所得者に交付される「源泉徴収票」とは大きな違いがあります。
源泉徴収票は、雇用契約に基づいて支払った給与について、従業員本人に交付することが法律で義務付けられています。それに対して、支払調書は業務委託契約などのいわゆる「外注(個人事業主・法人への契約支払い)」や「フリーランス」との取引で報酬や支払いのために作成されます。
そのため、支払先への交付義務が定められていません。源泉徴収票は郵送してでも届けることが義務です。しかし、支払調書の場合はその義務自体がありません。
義務がなくても郵送する3つの理由
実務上では支払い相手に支払調書の写しを郵送するケースがあります。その理由は以下の3つです。
1つ目は、フリーランスや外注先が確定申告を行う際に、自身の収入証明や取引実績の確認資料として支払調書を必要とするためです。
もちろん、フリーランス側でも請求書や通帳の入金記録を基に帳簿を作成することは可能です。しかし、取引先からの正式な支払調書があると、申告内容の裏付け資料として役立ちます。
そのため、税務署に提出する控えとは別に、フリーランス本人から「支払調書を送って欲しい」と要望されることがあるのです。
2つ目の理由は、取引の透明性を確保するためです。企業のコンプライアンス(法令遵守)や、経理処理の一貫性を保つための社内方針で渡すことが事前に決まっています。
特に規模の大きい法人では、支払調書の控えを受取人にも送付することで、後日取引内容や金額をめぐるトラブルを未然に防ぐ目的があるのです。確定申告の時期に問い合わせ増加への対応を事前に軽減する意図もあるでしょう。
支払い相手に郵送する場合の注意点
受取人に送る際には下記の注意点があります。まず、受取人本人に渡す支払調書にはマイナンバーを記載しないようにすることです。税務署へ提出する支払調書には受取人のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があるため、混同しやすいでしょう。
これらは、個人情報保護の観点から義務付けられているルールとなり厳守が必須となります。違反すると企業の法的な責任が問われることもあるため要注意です。
また、送付方法については、紙の郵送だけでなくPDFによるメール添付でも可能です。郵送の場合は、普通郵便で送るよりも、簡易書留や特定記録郵便など、配達記録が残る方法を選ぶと受取確認や郵送事故などへの対策として安全です。
支払調書は税務署などに郵送する必要があるか
支払い相手ではなく、税法の義務となる税務署の場合の郵送については、気になる方も多いでしょう。結論として、支払調書は事業者の所在地を管轄する税務署に「提出」する義務があります。
提出方法には「郵送」も含まれますが、近年では電子申告が進められています。特に、一定の件数を超えると任意ではなく、電子郵送が義務化されます。
それから、支払調書の提出期限は、報酬や料金を支払った年の翌年1月31日までです。この期日までに、所定の様式に基づいて支払調書を作成し、法定調書合計表とともに税務署に提出する必要があります。
期限を過ぎると、税務署からの指導や、場合によっては罰則の対象となるため、注意が必要です。
郵送の可否
次に、その提出方法に「郵送」が可能か、という点についても確認が必要です。支払調書は通常、郵送でも提出可能です。支払調書の枚数が少ない場合や、電子申告の準備が整っていない小規模事業者などです。また、光ディスクそのものの郵送もできます。これらの郵送による提出は、書類に不備がない限り有効な手段です。
ただし、事業者によっては電子申告(e-Tax)による提出が義務化される条件があります。例えば、以下の条件に該当する場合には、郵送ではなく電子提出が必須です。
- 令和3年分以降、1種類の法定調書が100枚以上
- 令和9年以降、30枚以上で電子申告が義務化
支払調書の枚数が多くなるほど、郵送ではなく電子申告による提出が求められるように変化しています。
ちなみに、支払調書は税務署以外の機関(市区町村役場、社会保険事務所など)に提出する必要はありません。郵送や電子送付の提出先は、あくまで国税庁が管轄の「税務署」のみです。
「法定調書合計表」の添付が不可欠
税務署への提出書類には「法定調書合計表」の添付が必須です。この合計表には、支払調書や給与所得の源泉徴収票などの内容を集計し、報酬支払人数、総額、源泉徴収額の合計などを記載します。
合計表を忘れて提出すると、税務署から差し戻されることがあります。
郵送する場合の方法
支払調書を税務署に郵送で提出する場合、その手順と注意点があります。
書類様式の用意
まず、国税庁のホームページから「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と「法定調書合計表」の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
支払調書は支払先ごとに1枚ずつ作成し、控えも用意しておくと後日確認が必要になった際に役立ちます。
「法定調書合計表」の同封
記入が完了したら、提出用の書類と一緒に、「法定調書合計表」を同封します。この合計表がないと、提出書類は受理されません。
返信用封筒の用意
また、控えにも収受印を押して返送してもらいたい場合は、返信用封筒(切手貼付・住所氏名記載)も添えましょう。
封筒には「法定調書在中」と朱書きし、提出先の税務署宛に郵送します。普通郵便でも送れますが、確実に届いた記録を残したい場合は、簡易書留やレターパックを利用するのがおすすめです。
提出期限
これらの提出期限は翌年1月31日までです。郵送の場合、消印ではなく、届いた日が提出日となります。
期限内に税務署に届くよう、余裕を持って郵送手続きを行いましょう。郵送方法に特別なルールはありませんが、記入漏れや添付漏れには十分注意し、正確な書類を提出することが大切です。
公益情報システムの「謝金システム」を活用しよう
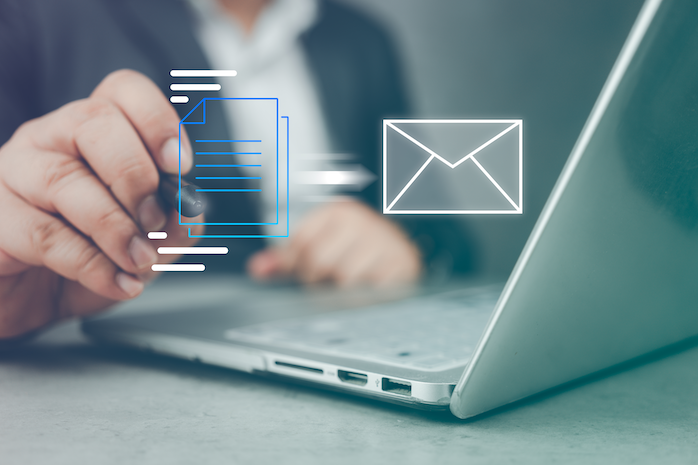
支払調書のを発行・提出する際に、便利な会計システムのツールがあります。それが公益情報システム株式会社の「謝金システム」です。
全法人が利用可能となっており、謝礼金や報酬の支払で発生した支払調書を作成し、それを「講師マイページオプション」を通じて相手に郵送することなく交付・閲覧することができます。
支払調書の郵送のまとめ
支払調書を郵送する場合は、任意の支払い相手に交付する場合と、税務署に送る場合の2つのケースがあります。
慣例として支払い相手に発行して任意で交付する場合も珍しくありませんが、税務署には税務書類の義務として提出が必要となります。
添付書類や郵送の仕方などの注意点を踏まえて、期限内に届くように郵送しましょう。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




