「電子帳簿保存法の法改正について理解を深めたい」と考えている方も多いでしょう。電子帳簿保存法とは、帳簿書類を紙ではなく、電子データで保存する制度のことです。2022年に法改正があり、内容の理解が難しいと方も少なくありません。
この記事では、制度の概要から改正の背景、実務上の対応まで詳しく解説していきます。電子取引やペーパーレス化が進むなかで、企業にとって無視できない法律である「電子帳簿保存法」について、正確に理解を深めましょう。
謝金システムでは、帳票の整合性を確保しながら、事務負担の軽減とコンプライアンスの両立が可能なシステムになりますので、ぜひご覧ください。
電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、1998年に制定され、帳簿書類を電子データとして保存する際の要件を定めた法律のことです。国税関係の帳簿や書類を紙ではなく、電子データで保存することを認める一方で、税務調査などへの対応条件が細かく規定されています。
「帳簿」と聞くと、仕訳帳や総勘定元帳など、会計上の記録が思い浮かぶかもしれません。これらの帳簿を、パソコンの会計ソフトやクラウドサービスを使って作成・保存することが一般的になってきた中、電子帳簿保存法は複数の書類を紙で印刷せずにデータのまま保管することを認めるためのルールとして整備されました。
どんな形式のデータ保存でも良いわけではありません。電子帳簿保存法では、データの真正性・可視性・検索性といった要件が求められます。
電子帳簿保存法の法改正がされる理由とは

電子帳簿保存法が改正されるに至った背景には、日本全体で進められている「デジタル化の推進」と「税務行政の効率化」が挙げられます。国税庁は、紙ベースの帳簿や書類をデジタルに置き換えることで、企業の事務負担を軽減しつつ、税務調査や情報収集をより効率的に行うことを目指しています。
また、電子取引の急増により、紙での保存に対応しきれないケースが増えたことも大きな要因です。取引先から請求書や領収書をPDFやメール添付で受け取る機会が増えた中で、それらを紙で出力して保存するという従来の方法では、非効率かつ不正防止の観点からも不十分ともいえます。
こうした課題に対応するため、電子帳簿保存法はデジタル環境に適応した制度へと段階的に改正されてきました。
電子帳簿保存法の法改正による対象書類
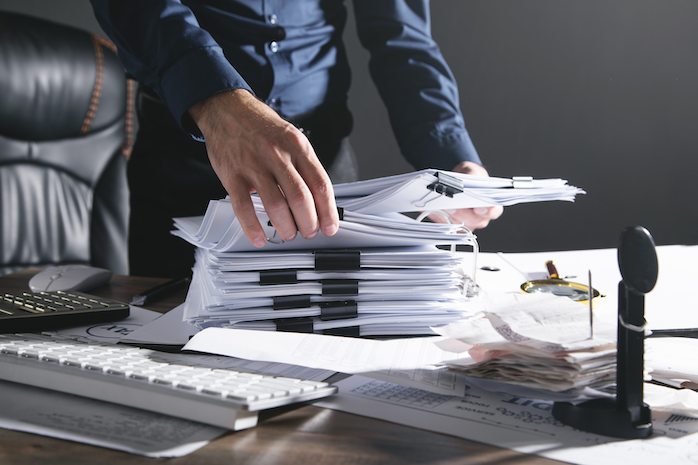
電子帳簿保存法の対象となるのは、大きく分けて以下のデータです。
| 対象書類 | 概要 |
|---|---|
| 帳簿・決算関係書類 | 帳簿や仕訳帳、試算表などを電子的に保存することを認める制度のこと。申告加算税の軽減措置が適用可能。 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書や請求書をスキャンし、画像データとして保存する方法のこと。 |
| 電子取引データの保存 | 請求書や領収書などをPDFやメールで受け取った場合、そのデータをそのまま保存するルールのこと。法改正により厳格化された。 |
電子帳簿保存法は「すべての企業」に関係する法律であり、特に電子取引を日常的に行っている企業にとっては、実務に直結する重要な制度です。
電子帳簿保存法の3つの法改正の内容

電子帳簿保存法は、2022年に法改正、2024年に完全義務化が実施されたことで、実務への影響が非常に大きいものとなりました。ここでは、法改正によって実際に何がどう変わったのかを、制度の区分ごとに具体的に整理していきます。
①電子帳簿・決算関係書類の保存制度の改正
保存制度の改正により、帳簿や試算表、総勘定元帳といった電子帳簿を保存する場合の手続きが簡素化されました。従来は、「事前に税務署へ届出書を提出する」手続きが必要になりましたが、2022年1月1日の改正により、優良な電子帳簿であれば届出は不要となりました。
この「優良な電子帳簿」とは、真実性と可視性が確保されている帳簿のことで、改ざん防止のためのタイムスタンプや訂正・削除履歴の管理ができるものに該当します。会計ソフトで自動記録されたデータをそのまま保存する運用であれば、比較的ハードルは高くありません。
ただし、税務署への届出が不要になったからといって、何のルールもなく保存できるわけではないため、注意しましょう。
②スキャナ保存制度の緩和
紙で受け取った請求書・領収書などをスキャンして保存する「スキャナ保存」についても、要件が大きく見直されました。
これまでは、スキャナ保存を行うために細かな運用ルール(例えば、スキャン後の原本保存期間や相互牽制体制など)が定められており、導入のハードルが高い制度でした。2022年の法改正により、入力期限や業務処理規程の整備があれば、スマートフォンや複合機を用いた簡易スキャンでも対応できるようになります。
さらに、紙の原本保存は不要となり、画像データだけを所定の要件で保存すればよいとされています。これにより、経費精算業務や社外での領収書処理が格段に効率化される現状になりました。
③電子取引データの保存義務化
電子取引の電子保存義務化は、2024年1月1日から正式に施行され、2026年1月までの2年間は猶予期間として運用されています。
これまで、メールやウェブシステムで受け取った請求書や領収書などの電子データを紙で印刷して保存していた企業も多くありました。電子帳簿保存法改正により、電子取引データは電子データのまま保存しなければならないと定められました。
保存義務化では、「保存データにタイムスタンプを付与する」「保存データの訂正・削除履歴を残す」「社内規定(事務処理規程)を作成し、業務フローの中で改ざん防止措置を講じる」ことの3点のいずれかが求められる形になります。
法改正された電子帳簿保存法によりやらなくてはならない5つのこと

電子帳簿保存法の改正により、事業者は従来以上に明確かつ具体的な対応が求められるようになりました。特に電子取引に関する保存義務化が本格適用されることで、企業規模を問わず「今まで通りでは済まされない」状況が生まれています。
ここからは、法改正に対応するために必要となる実務的な対策や社内で準備すべき内容を整理し、何をどこから着手すべきかを具体的にご説明します。
電子取引データを紙で保存している場合の対応見直し
これまでメールやWeb上で受け取った請求書・領収書を「印刷してファイル保管」していた場合、2024年の改正以降はこの方法が認められなくなります。なぜなら、電子帳簿保存法により、PDFなどで受け取った書類は、電子データのまま、要件を満たした方法で保存することが義務となったからです。
まず行うべきことは「電子取引の流れを洗い出すこと」です。どの部署で、どのような形式で、どの取引先から電子データを受け取っているかを整理し、それぞれの対応方針を決め、実行する必要があります。
3つの保存要件のどれを対応するか決める
電子データの保存方法として、以下の3つのいずれかが求められます。
- 保存データにタイムスタンプを付与する
- 保存データの訂正・削除履歴を残す
- 社内規定(事務処理規程)を作成し、業務フローの中で改ざん防止措置を講じる
まずは、自社がどの方法を選ぶかを検討しましょう。対応方法が決まれば、それに応じた運用ルールを整えられます。
保存先やファイル名のルールを決める
電子帳簿保存法では、ファイルを検索できる状態で保存しておくことが求められます。検索項目としては「取引日」「取引先」「金額」などが基本であり、これらを管理できるフォルダ構成やファイル名の命名規則を整備する必要があります。
たとえば、「2025-07-31_ABC株式会社_請求書_33000.pdf」のように、日付・取引先・内容・金額をファイル名に組み込む方法で、検索要件を満たす形にするケースもあります。
また、保存先についても、担当者の個人フォルダではなく、社内共有ドライブやクラウドストレージなど、複数人が閲覧可能で変更履歴が残せる環境を選ぶことが推奨されます。
社内マニュアルや担当者教育を行う
運用を円滑に行うためには、保存ルールを社内で文書化し、関係する部門や担当者にしっかり共有する必要があります。マニュアルの形にまとめておけば、担当者が変わったときにもスムーズに引き継ぎすることができ、法令違反のリスクを防げるからです。
また、社内において電子帳簿保存法に関する基本知識や具体的な操作手順についての説明会や研修を行うことで、制度に対する理解を深めることができます。
クラウドサービス・業務支援ツールの導入検討
電子データの保存や検索要件への対応には、クラウド型の文書管理サービスや、電子帳簿保存法対応の支払管理システムの導入も有効です。
たとえば、謝金処理や謝礼支払いが多い法人・団体においては、公益情報システムが提供する「謝金システム」のようなツールを活用することで、帳簿データの自動保存や一括出力、記録の一元管理が可能となり、改正法への対応もスムーズに進められます。
こうしたツールの活用は、単なる法令対応だけでなく、経理業務の効率化・属人化の回避にもつながるメリットがあります。
電子帳簿保存法の法改正についてまとめ
電子帳簿保存法の概要から始まり、法改正の背景、具体的な改正内容、そして企業がやらなければならない対応について、順を追って解説しました。2022年に法改正、2024年に義務化と立て続けに実施された法改正により、電子帳簿保存法は制度としての実効性が強まり、すべての事業者が対応を迫られる重要な法律となりました。
電子帳簿保存法の適切な理解・対応をするためには、社内でのルール整備や社員教育に加え、業務支援システムの活用が有効です。たとえば、講師や取材協力者などへの謝礼金処理を行う法人では、以下のような電子帳簿保存法に対応した「謝金システム」のようなツールを導入することも1つの方法です。
謝金システムでは、帳票の整合性を確保しながら、事務負担の軽減とコンプライアンスの両立が可能になります。電子帳簿保存法に適した人材確保が難しい場合は、謝金システムのようなツールを導入してみてはいかがでしょうか。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




