大学で教えるという選択は、専門性を活かすだけでなく、社会貢献としても意義のある働き方です。一方で、雇用形態が常勤とは異なるため、事前に知っておくべき制度や注意点も多く存在します。
この記事では、大学非常勤講師の実態から平均給料・報酬の管理までをわかりやすくお伝えします。
大学の非常勤講師とは?

大学の非常勤講師とは、週に数コマから担当する授業を受け持ち、常勤教員とは異なり任期や勤務時間が限定されている講師のことを指します。多くの場合、他の大学や企業などで本業を持ちながら、専門知識や実務経験を生かして講義を行っている方が多く在籍しています。中には研究者や退職後の専門家が担当するケースも多く、柔軟な働き方が可能な職種といえるでしょう。
一般的に非常勤講師は大学の正規教員ではなく、年度ごとの契約更新制であることが多いです。担当する科目数や授業の難易度、大学の規模などによって業務内容は変わりますが、基本的には講義の準備、授業の実施、簡易な成績評価までが主要な業務範囲となります。
また、雇用契約はあくまで「授業単位」で交わされるため、非常勤講師は勤務時間に対して給与が支払われるのではなく、授業1コマあたりの報酬で管理されているのが特徴です。このため、給与の計算方法や支払いタイミングも、常勤教職員とは異なる点に注意が必要です。
非常勤講師は教育現場における多様性の確保にも寄与しており、学生にとっても実務家や異分野の視点を得る機会となっています。今後はさらに、リスキリングや社会人教育の一環としての登壇機会も増えると考えられており、ますます注目される働き方となっていくでしょう。
大学の非常勤講師の給料の平均
大学の非常勤講師の給料は、勤務先の大学や地域、講義内容によって異なりますが、基本的には「1コマ(90分程度)あたりの報酬」で計算されるのが一般的です。全国的な平均としては、1コマあたり5,000円〜12,000円程度の報酬が支払われているとされ、国公立大学よりも私立大学のほうがやや高めに設定されている傾向があります。
たとえば、ある私立大学では1コマあたり8,000円前後、国立大学では6,000円前後が多く見られます。ただしこれは講義単価であり、月給や年収ベースで考えると授業数によって大きく変動します。週に2コマ担当した場合、1ヶ月の講義は8〜9回程度になるため、月額でおよそ50,000円〜100,000円程度の報酬になるケースが一般的です。
また、講義の回数や担当する授業の数が増えればその分収入も増えますが、非常勤講師という立場上、大学によっては担当できる上限コマ数が定められている場合もあり、副業としての位置づけで活動している方も少なくありません。
以下は、大学種別と平均的な1コマ報酬の目安を示した表です。
| 大学の種別 | 1コマ(90分)あたりの報酬の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 約5,000〜7,000円 | 教養科目・専門科目で差がある |
| 公立大学 | 約6,000〜8,000円 | 地域や財政状況で異なる |
| 私立大学 | 約7,000〜12,000円 | 名門校ほど高い傾向にある |
このように非常勤講師の報酬は「定額制の給与」ではなく、授業ごとの成果に対する報酬として位置づけられており、教育への熱意や専門性をもって貢献することで、一定の収入を得る働き方となっています。
大学の非常勤講師の報酬の支払い方

大学の非常勤講師に支払われる報酬は、一般的に「謝金」として処理されることが多く、給与とは異なる取り扱いとなるケースも少なくありません。報酬の支払い方法には大学ごとのルールがありますが、年度契約のもとで「授業を実施した月の翌月」あるいは「学期末」などにまとめて支払われる形式がよく見られます。
報酬の支払いにあたっては、源泉徴収が行われるのが基本です。たとえば、講師謝金として支払う場合、支払額から一定の源泉所得税(10.21%など)が控除され、残額が銀行口座へ振り込まれます。また、年間で一定金額を超える場合は、大学から「支払調書」が発行され、確定申告の際に必要な書類として使われることになります。
なお、大学によっては、勤務日ごとの「出勤簿」や「報告書類」の提出が求められることもあり、手続きが煩雑になるケースもあります。非常勤講師は授業準備だけでなく、こうした事務的な作業も一部担うことになりますので、あらかじめ流れを把握しておくことが大切です。
特に、非常勤講師の人数が多い大学や、複数のキャンパスを持つ大学などでは、報酬管理のシステム化が進んでおり、専用のツールを通じて講義の実施記録や報酬申請を行うスタイルも増えてきました。こうした仕組みを取り入れることで、大学側の処理負担も軽減され、講師側も報酬の受け取り状況が明確になるというメリットがあります。
謝礼金の相場に関しては下記記事でも解説しています。
大学の非常勤講師への支払いに便利なソフト
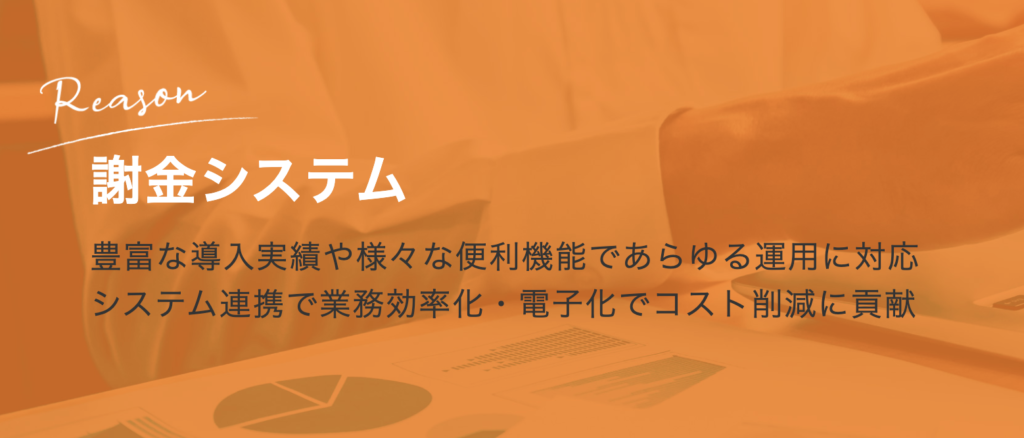
大学で多数の非常勤講師を雇用している場合、講義回数に応じた謝金の計算や源泉徴収、支払調書の作成など、報酬管理は複雑化しがちです。こうした業務を効率化するうえで注目されているのが、公益情報システムが提供する「謝金システム」です。
この「謝金システム」は、非常勤講師や外部講師への報酬支払いに特化したクラウド型ソフトであり、大学や研究機関、自治体などでの導入が進んでいます。以下のような特徴を備えており、報酬処理に関する作業を一括でサポートしてくれます。
まず、講師1人ひとりの講義実績や契約内容に基づいて、支払額と源泉徴収税額の自動計算が可能です。これにより、人的ミスの発生を抑え、正確な報酬計算が実現できます。さらに、講師別・講義別に支払記録を一元管理できるため、事後の確認や支払調書の作成も非常にスムーズです。
また、「謝金システム」はマイナンバー制度への対応もされており、講師からの情報収集や適正管理の手間を大幅に軽減できます。紙での申請やExcel台帳といった従来の煩雑な作業を減らし、クラウド上で完結できる点も魅力です。
講師数が多くなるほど業務は複雑になりますが、このシステムを活用すれば、庶務担当者の負担を減らしつつ、講師への正確な支払いと透明性のある処理が可能になります。詳細は、以下の公式ページをご覧ください。
大学の非常勤講師についてまとめ
大学の非常勤講師は、専門知識や実務経験を活かして教育に貢献する重要な役割を担っています。常勤教員とは異なる契約形態ではありますが、柔軟な働き方ができる点や、教育現場での実践を通じて社会との接点を保ち続けられる点など、多くの魅力を持っています。
報酬については、1コマあたりの支給単価に基づく形が一般的で、大学の種別や地域によって差があるものの、国公私立問わず幅広く人材を求めているのが現状です。講義の内容や頻度に応じて、月々の収入は大きく変わるため、自身のライフスタイルにあわせて働き方を選ぶことが求められます。
また、報酬の支払い方や源泉徴収、支払調書などの手続きについても、一般的な給与とは異なる部分があり、講師自身もある程度の理解を持っておく必要があります。大学側も事務処理の簡素化・ミス防止のために、謝金管理システムを導入する動きが進んでおり、正確かつ効率的な報酬処理の体制づくりが重要視されています。
特に、「謝金システム」のような専門ソフトを活用することで、大学の事務負担は大きく軽減され、講師にとっても報酬の受け取りや確認がスムーズになります。こうした仕組みの導入は、教育現場の質向上にもつながっていくはずです。
今後、社会人教育や実務家教員の登壇機会が増えるなかで、非常勤講師のニーズはさらに高まると考えられます。制度や支払い方法について正しく理解し、安心して教育に携われる環境を整えることが、大学側にも講師側にも求められている時代です。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




