企業が研修などで講師にセミナーや講演会を依頼した際には、企業は講師に対して報酬を支払いますが、税務における報酬はマイナンバーの対象になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では講師の報酬にマイナンバーが必要かを検証し、必要な理由や注意点、税務会計におすすめのソフトも紹介します。
講師の報酬にマイナンバーは必要?
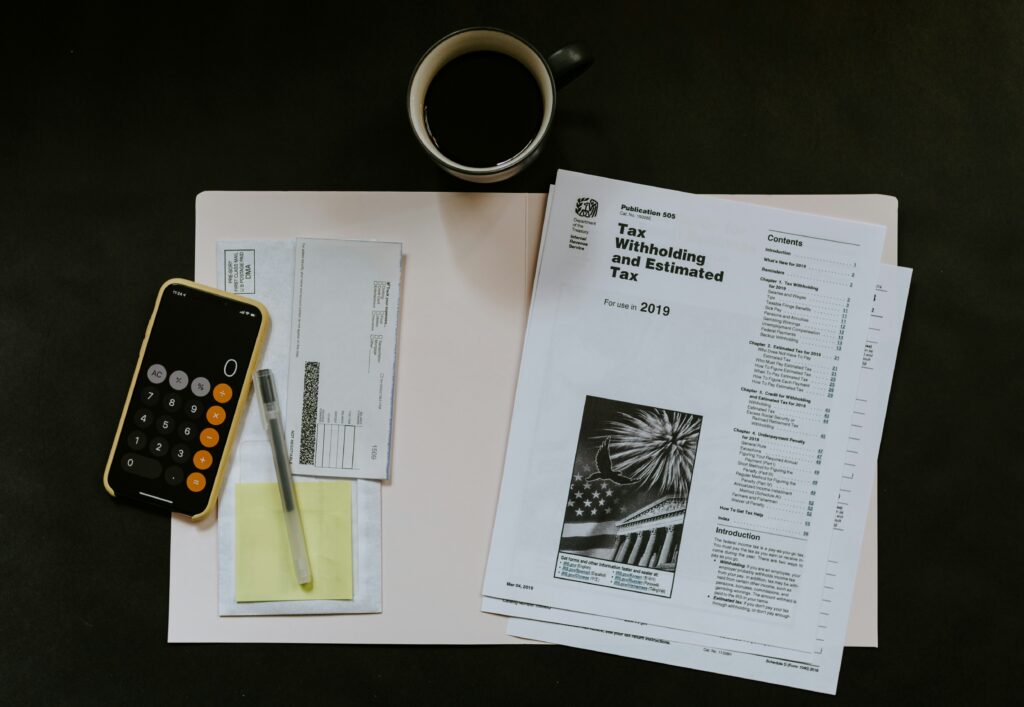
結論からいうと、講師への報酬支払いには原則としてマイナンバーの提出が必要とされています。
事業者は所得税法に基づいて報酬から源泉徴収を行い、源泉徴収票や支払調書を作成して税務署へ提出しなければいけません。
源泉徴収や支払調書などの書類に講師のマイナンバーを記載して提出するので、講師に提供を依頼することになります。
一方で少額な報酬や一時的な支払いなど、一部例外的なケースもあるので注意が必要です。
講師への報酬が年間で5万円を超える場合に支払調書の提出が必要となるので注意しましょう。
講師の報酬にマイナンバーが必要な理由
講師の報酬にマイナンバーが必要な理由として、以下の4つの項目が挙げられます。
- 所得税の源泉徴収のため
- 社会保険の手続きのため
- 支払調書の作成・提出のため
- 正確な税務処理を行うため
マイナンバーが必要な理由を確認し、適切な税務処理を行いましょう。
①所得税の源泉徴収のため
講師への報酬からは所得税の源泉徴収が必要なため、支払者は受取人である講師の個人情報を正確に把握しなければいけません。
源泉徴収した所得税額や講師の情報を記載する源泉徴収票は税務署へ提出する義務があり、その際に識別番号が記載されたマイナンバーの記載が不可欠です。
このようなマイナンバー手続きにより、税務署は個人の所得を正確に管理して適正な課税ができます。
②社会保険の手続きのため
講師が事業者と雇用契約を締結している場合、雇用保険や労災保険などの社会保険の適用を受ける際に、事業者はその加入手続きを行わなければいけません。
これらの手続きにおいては、被保険者となる講師の個人情報を正確に届け出るためにも氏名や住所だけでなく、個人の加入状況が一元的に管理したマイナンバーを利用します。
一方で業務委託契約における講師報酬の場合は、社会保険の手続きにマイナンバーは不要ですので事前に確認しましょう。
③支払調書の作成・提出のため
事業者が年間で一定金額を超える講師への報酬を支払った場合、所得税法に基づき、その支払金額や講師の氏名・住所などを記載した支払調書を税務署に提出しなければいけません。
支払調書は税務署が個人の所得を把握し、適正な課税を行うための重要な資料となります。
支払調書に講師のマイナンバーを記載することで、税務署は個人を正確に識別したうえでの所得情報の照合が可能です。
④正確な税務処理を行うため
マイナンバーは講師の報酬に関する、正確な税務処理を実現するために必要な手続きです。
源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載することで、税務署は個人の所得情報をほかの情報と正確に紐付けることが可能になり、所得の申告漏れや過少申告を防止できます。
一方事業者側としては、正確な情報に基づいた事務処理が実現され、誤った税務処理による追徴課税などのリスクを軽減できるのもメリットです。
講師の報酬のマイナンバー手続きにおすすめのソフト
ここまでに紹介したように、講師の報酬に対しての税務処理に関してはマイナンバーの登録が必要ですが、面倒な手続きや税務処理を行わなければいけません。
そこでおすすめなのが公益情報システム株式会社が提供する、講師や臨時職員への謝礼金・報酬支払い業務を効率化する公益法人向けの会計ソフト、「謝金システム」です。
簡単な操作で支払明細や領収書の作成が可能で、会計システムとの連携により仕訳作業の負担を軽減します。
支払調書や源泉徴収票の印刷、インボイス制度への対応やExcel形式でのデータ出力など、多彩な機能を備えているのも強みです。
クラウド版とオンプレミス版の両方が提供されており、団体のニーズに応じた柔軟な運用が可能で、公益法人の謝金支払い業務を効率的かつ正確にサポートします。
マイナンバー手続き後の、スムーズな税務処理をサポートしてくれるのでぜひお試しください。
講師の報酬のマイナンバーの取得の注意点

講師の報酬に関し、マイナンバー手続きを行う際には以下の5点に注意しなければいけません。
- 利用目的を限定して明確にする
- 提供の強制は避ける
- 本人確認を徹底する
- 情報漏洩に注意
- 利用後は適切な方法で廃棄する
注意事項を遵守してマイナンバーを取得し、適切な税務処置を行ってください。
利用目的を限定して明確にする
講師からマイナンバーを取得する際には、利用目的を明確に限定して講師に丁寧に伝えましょう。
マイナンバーが必要な理由や源泉徴収票の作成や税務署への提出など、マイナンバーの利用意図を明確に説明して、講師の不安を軽減すれば理解と協力を得やすくなります。
法律で定められた目的以外の利用は厳禁であることを強調し、事業者が取得したマイナンバーを適切に管理する姿勢を示すことで強い信頼関係の構築も可能です。
マイナンバーの提供を拒否された場合について
講師の中には、マイナンバーの提出を許可する方もいます。
事業者は、法定調書にマイナンバーを記載する義務があるため、講師からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
国税庁のHPによると、「契約先は、収集したマイナンバーを『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません。」と記載されています。
そのため、必ずマイナンバーを提供してもらうようにしましょう。
本人確認を徹底する
講師からマイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防いで正確な情報を確保するための本人確認も徹底しましょう。
具体的には、マイナンバーカードの提示や顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の提示、またはそれぞれのコピーを提出してもらうなどの措置を講じます。
このような措置により、提供者が確かにそのマイナンバーの持ち主本人であることを確認し、誤った情報による税務処理や情報漏洩のリスクを低減することも可能です。
情報漏洩に注意
講師から取得したマイナンバーは重要な個人情報で、情報漏洩により大きな社会問題に発展する可能性もあるので注意が必要です。
情報漏洩を防ぐためにも、事業者はマイナンバーの取得時から保管や利用、廃棄に至るまで、徹底的な安全管理措置を講じましょう。
具体的な措置としてアクセス権限の厳格な管理や保管場所の限定、暗号化などの技術的対策や従業員への情報セキュリティ教育の徹底などが挙げられます。
利用後は適切な方法で廃棄する
講師の報酬に関するマイナンバーは法定の保管期間が過ぎるなど、不要になった際には速やかにかつ適切な方法で廃棄しましょう。
ゴミ箱に捨てるような行為は厳禁であり、シュレッダーによる裁断に加えてデータであれば復元不可能な方法での削除など、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための措置を講じなければなりません。
マイナンバー情報の適切な廃棄処理を徹底することで、不要になったマイナンバーが第三者の手に渡り、不正利用される危険性を抑制できます。
講師への報酬支払はマイナンバーを適切に取得しよう
講師への報酬も課税対象になるため、講師にマイナンバーの取得を依頼しなければいけません。
講師への報酬支払が生じた際には、本記事を参考にしてマイナンバーを取得して適切な税務処理を行ってください。
謝金に関する、マイナンバー取得手続後の税務処理をスムーズに進めたい方は、謝礼金・報酬支払い業務を効率化する公益法人向けの会計ソフト、「謝金システム」の導入がおすすめです。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




