電子帳簿保存法に対応して書類を保存する際、「必要な対象書類についてよくわからない」「対象書類の保存方法を教えてほしい」という方も多いでしょう。電子帳簿保存法は義務化され、多くの事業者が遵守する必要がある法律になります。対象書類に関する理解が乏しいと、必要書類と保存方法について検討することができません。本記事では電子帳簿保存法の対象書類を全て紹介します。保存方法やおすすめのソフトについても紹介するので、要件と合わせてチェックしましょう。
電子帳簿保存法の対象書類一覧!

電子帳簿保存法では、以下のフェーズで対象書類が異なります。
- 国税関係帳簿
- 国税関係書類
- 電子取引
3つのフェーズごとに必要な書類について、紹介していきます。
1.「国税関係帳簿」
国税関係帳簿とは、日々の業務のなかで作成する帳簿資料のことです。電子帳簿保存法における必要な国税関係帳簿は、以下の書類です。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 売上帳
- 売掛帳
- 仕入帳
- 買掛帳
- 給与台帳
- 棚卸帳簿
- 領収書控え
- 減価償却資産台帳
- 支払調書(法定調書)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 事業資金の出納帳簿
- 預金出納帳
- 税務申告書関連資料
- 固定資産台帳
これらの書類は、「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)」の区分に該当します。データでの保存は任意になるため、紙で保存・管理する形でも問題ありません。
2.「国税関係書類」
国税関係は、「決算関係書類」「取引関係書類」によって、必要書類が異なります。それぞれの区分で必要な書類は、以下の通りです。
| 決算関係書類 | ・棚卸表 ・減価償却計算書 ・貸借対照表(財務諸表) ・損益計算書(財務諸表) ・税務申告書とその添付書類 ・記帳の基礎資料(メモ書き、計算書類) ・株主総会議事録 |
| 取引関係書類(自社発行(写し)) | ・領収書控え ・請求書控え ・納品書控え ・預金通帳控え ・預り証控え ・小切手控え ・約束手形控え ・社債申込書控え ・有価証券(商品以外)控え、有価証券受渡 ・計算書控え ・輸出証明書控え ・契約の申込書(定型的約款無し)控え ・契約書控え ・見積書控え ・検収書控え ・入庫報告書控え ・貨物受領証控え ・注文書控え ・株式申込書控え ・仕入明細書控え ・売上明細書控え ・給与明細書控え ・源泉徴収票控え ・支払調書控え ・交通費精算書控え |
| 取引関係書類(取引先発行) | ・領収書 ・請求書 ・納品書 ・預金通帳 ・預り証 ・小切手 ・約束手形 ・社債申込書 ・有価証券(商品以外)、有価証券受渡計算書 ・輸出証明書 ・契約の申込書(定型的約款無し) ・契約書 ・見積書 ・検収書 ・入庫報告書 ・貨物受領証 ・注文書 ・株式申込書 ・仕入明細書 ・売上明細書 ・給与明細書 ・源泉徴収票 ・支払調書 ・交通費精算書 |
取引関係書類は、取引先からの書類だけでなく、自社が作成した請求書や納品書の写しも該当します。取引関係書類のうち、紙で受け取った書類や紙で作成した書類は「スキャナ保存」の対象になるため、データ保存が必要になります。
3.「電子取引」
電子取引とは、電子メールやクラウドサービスなどを活用し、取引した書類のことです。対象となる書類は、国税関係書類の「取引関係書類」と同じです。電子帳簿保存法では、電子取引で発生した書類のデータ保存が義務化されています。したがって、紙の書類はそのまま保存できます。ちなみに、電子取引以外では、電磁的記録やスキャナ保存といった電子保存が認められる「国税関係帳簿」「国税関係書類」の書類も対象となります。
電子帳簿保存法の対象外となる書類一覧

電子帳簿保存法の対象外となる書類は、手書きで作成された帳簿・書類です。紙の書類は対象外になるため、スキャン保存などの保存方法を駆使する必要があります。手書きの帳簿や書類は、簡単に破棄できません。一定期間の保存が必要になるため、社内で保存方法について決めておく必要があります。
電子帳簿保存法における対象書類の保存方法一覧

電子帳簿保存法は義務化され、書類の保存方法を社内で明らかにしておくことが大切になります。電子帳簿保存法に対応した対象書類の保存方法は、以下の3つです。
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引
それぞれ、順番に確認しましょう。
電子帳簿等保存
電子帳簿等保存では、パソコンで作成した帳簿の対象書類を保存する場合に守るべき要件が定められています。電子帳簿等保存の要件は、以下の3つです。
- 要件1.システム関係書類等(システムの概要書や仕様書、操作の説明書、事務処理のマニュアル)を備え付ける
- 要件2.保存場所に電子計算機やプログラムと操作の説明書を備え付け、「整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力」できる
- 要件3.税務職員からの質問検査の際、電子データのダウンロード要求に対応できる
電子帳簿等保存の要件を手動で満たすのは、至難の業です。会計ソフトをダウンロードし、ソフト上で帳簿の作成やデータ入力をすることで要件に沿った保存が可能になります。
ソフトによっては電子帳簿等保存で求められる「優良」認定を受けられる他の要件(検索機能要件など)を満たせる場合もあります。
スキャナ保存
スキャナ保存とは、紙で受け取った書類をスキャンして保存する方法のことです。スキャナ保存の場合、契約書、納品書、請求書などの「重要書類」と見積書、注文書などの「一般書類」で保存の要件が異なります。。スキャナ保存の要件は、以下の通りです。
- 要件1.入力期間の制限(書類を受け取っておおむね7営業日以内、最長2ヶ月以内の業務処理サイクルの期間の7営業日以内)
- 要件2.一定の解像度による読み取り(解像度200dpi以上)
- 要件3.カラー画像による読み取り(赤色、緑色、青色の階調で256階調以上・24ビットカラー)
- 要件4.タイムスタンプの付与(条件を満たせば省略可)
- 要件5.バージョン管理(改ざん防止のシステムの使用)
- 要件6.帳簿との相互関連性の確保(帳簿の記録とその関連性を確認できる)
- 要件7.見読可能装置等の備付け(14インチ以上のカラーディスプレイ、カラープリンタ、操作説明書を備え付ける)
- 要件8.速やかに出力すること(整理された形式で出力、元の書類と同じ程度に鮮明な表示、拡大や縮小での出力が可能、文字サイズが4ポイントでも読める)
- 要件9.システム概要書等の備付け(スキャナ保存のシステムや手順を明確にするための概要書や操作マニュアルを整備する)
- 要件10.検索機能の確保(データのダウンロード要求に対応できる場合で、取引の日付、金額、取引先名を基準に検索できる)
スキャナ保存の要件には、文字の大きさや形状などが記載されています。また、運用上の規定も定められているため、スキャンを実施する従業員の教育と社内マニュアルの準備が必要になります。
電子取引
電子取引は、書類のすべてが電子帳簿保存法の対象となります。2025年現在、電子取引のデータ保存は義務化されたため、すべての事業者に対応が求められています。電子取引の要件は、以下の通りです。
- 要件1.改ざん防止の措置(orタイムスタンプの付与)
- 要件2.検索機能(日付・金額・取引先で保存・検索できる)
- 要件3.電子計算処理システムの概要書の備え付け
- 要件4.訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定める
電子取引の要件はシンプルで、書類を発行・受け取ったときに、保存するデータを削除・修正できないシステムを使っていれば問題ありません。嘘をつかないこと、分かりやすいことが求められるため、社内でデータの保存方法を定め、ルールを決めるようにしましょう。
電子帳簿保存法の対象書類の保存期間

電子帳簿保存法の対象書類には、保存期間が定められています。以下の形態によって、書類の保存期間は異なります。
- 法人
- 個人事業主(青色申告)
- 個人事業主(白色申告)
- 副業
1つずつ順番に解説していきます。
法人
法人の場合、帳簿類や取引に関連して作成・受領した書類は、7年間の保存が必要です。7年間は、確定申告書の提出翌日からを指します。そのため、書類を作成・受領した日付から7年間ではありません。
しかし、法人で青色申告書を提出している場合、10年間の保存義務が発生します。とはいえ、会社法上帳簿の保存期間は10年間なので、とりあえず10年間保存しておけば問題ありません。
個人事業主(青色申告)
青色申告をしている個人事業主の場合、帳簿は7年間、請求書や見積書などの書類は5年間の保存が義務付けられています。ただし、現金のやり取りが分かる領収書や小切手の控えなどは7年間の保存義務が設けられています。書類によって、7年と5年が混同するため、間違わないようにしましょう。
個人事業主(白色申告)
白色申告の個人事業主の場合、法定帳簿が7年間の保存義務が発生します。請求書や領収書、棚卸表などの書類は5年間になります。青色申告と異なり、保存義務が混同しないため、間違うことも少ないです。ただし、年度毎で申告方法を変えていると、保存期間も混同するため、申告方法に沿った保存期間を理解しておく必要があります。
副業
副業の場合、前々年分の業務にかかる雑所得の収入金額が300万円を超えていると、所得に関係する現金預金の書類は5年間保存する必要があります。間違えやすい方は、300万円を目安に、保存義務が発生することを理解しておくと良いでしょう。副業の場合、収入に関わらず、帳簿の作成や保存は義務ではありません。
電子帳簿保存法で対応書類を扱うときの注意点

電子帳簿保存法に対応する書類を保存する際、保存期限を守りましょう。スキャナ保存の場合、読み取り保存の期限が決まっています。そのため、期限を過ぎると要件を満たせなくなります。最長2ヶ月以内の業務処理サイクルの期間を設けており、その基準日から7営業日以内は保存が可能です。
また、手書きの「国税関係帳簿」は、電子保存のみができません。万が一、原本の紙書類を捨ててしまうと法令違反となります。パソコンで数字のデータを入力だけしてそれを保存しても、電子帳簿保存法では認められません。ただし、電子取引の場合は、紙書類の原本を保存する必要がありません。
電子帳簿保存法の対応書類の保存・管理におすすめなソフト2選
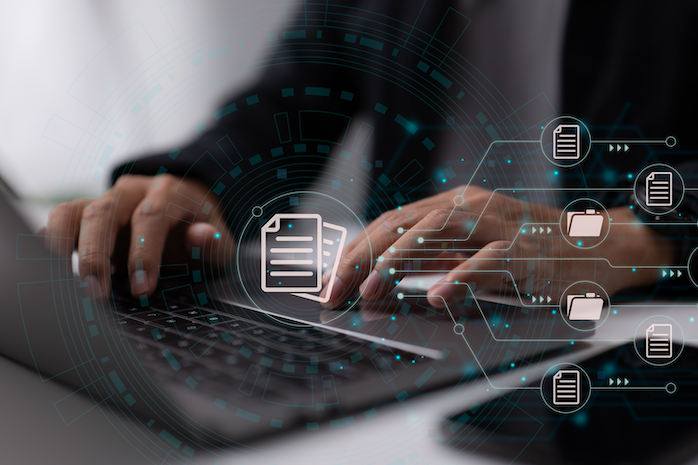
電子帳簿保存法に対応する場合、会計ソフトの使用が欠かせません。ここからは、電子帳簿保存法に対応しているおすすめの会計ソフトを2つ紹介します。それぞれ、順番に確認していきましょう。
WEBバランスマン
「WEBバランスマン」とは、公益情報システム株式会社が公益法人向けに提供している会計ソフトのことです。JIIMA認証を受けた「ClimberCloud」となっており、簿記の知識がなくても簡単に入力できるソフトになります。また、クラウド機能が使用できるため、データ保存に向いています。伝票を作成する際、請求書を一緒にアップするだけで電子帳簿保存法の要件を満たせます。
弥生会計オンライン
「弥生会計オンライン」とは、弥生株式会社が一般法人向けに提供する会計ソフトのことです。電子帳簿保存法に対応しており、タイムスタンプなしで電子取引の書類を保存できます。最新の法改正にも対応しているため、電子帳簿保存法の知識に乏しい方でも安心して使用できます。また、弥生会計オンラインでは、改ざん防止の要件の「訂正・削除の履歴確認」をシステムとして備えています。わかりにくい電子帳簿保存法への対応も容易なため、一般法人にもおすすめです。
電子帳簿保存法の対象書類の一覧についてまとめ
本記事では、電子帳簿保存法における対象書類について紹介しました。電子帳簿保存法では、区分によって対象書類が異なります。各区分で対象書類は多いため、適切な対策が行えていない法人や個人事業主は漏れが発生しやすいのが現状です。また、保存方法ごとに要件が定められています。そのため、自社に該当する区分と保存要件を確認しながら、書類を保存するようにしましょう。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




